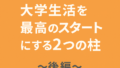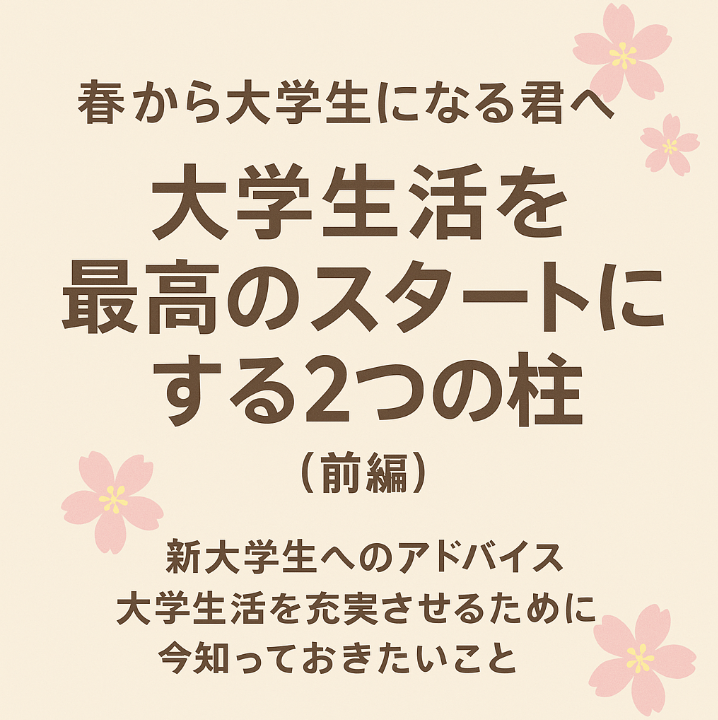
来る2月・3月は、3年前の高校入試に向けて一緒に勉強した高校3年生や、昨年は惜しくも希望の大学に合格できず1年の浪人生活を乗り越えた浪人生から、今年もたくさんの大学受験の合格の報告をもらいました。
この春から大学に進学される皆さん、本当におめでとうございます!!
これから徐々に授業も本格的に始まり、大学生活も忙しくなっていきますが、今後の大学生活を充実させるうえでこの4月・5月はとても重要な時期になってきます。
今回はこの春から新大学生になる皆さんに向けて、自分の経験も踏まえて、是非頭に入れておいてほしいことを「学習面」と「私生活面」の2つの柱というテーマで、前編・後編に分けてお伝えしたいと思います。もしかすると大学2・3年生や高校生にも役に立つ内容もあるかもしれません。もしこのブログを読んでいただいて、身近にいる人に役に立ちそうな内容がありましたら、是非その人に伝えてあげてもらえると嬉しく思います。
今回は大学生の「学習面」についてアドバイスをまとめてみます。
第1の柱:学習面でやっておくべきこと
① 履修した授業には極力すべて出席すべし!
「履修した授業には極力すべて出席すべし!」
高校を卒業したばかりの皆さんなら、何当たり前のことを書いてんだと思われると思います。しかしながら、大学の偏差値の高い低いにかかわらず、授業によっては回を追うごとに出席する生徒の数が少なくなっていくなんでこともしばしば。
高校と大学の学びの最大の違いは、「自分で考え、自分で行動する」スタイルであることであり、学部にもよりますが、私が卒業した法学部では授業の出欠も自由な場合も多く、高校と比較すると教員の目は1人1人に行き届かなくなります。
よく言われることですが、大学の先生は「教育者」ではなく「研究者」であり、自身の研究が最優先事項であり、「わかりやすい授業を提供すること」が必須ではありません。
しかしながら、私の経験では、どの教授も授業のことについて質問に行った際にはとても親切に教えてくれて、自主的に学ぶ姿勢がある学生にはとてもやさしかった印象があります。大学によっては、自分の学部以外の授業も選択できたり、他大学の授業も卒業単位に含めることができたりと、主体的にまなぼうとするならば、どこまでも深く学べる環境が大学にはあります。この春、自分なりの学び方について考えておくと、大学の授業にもスムーズに馴染めるでしょう。
➡授業は4回まで欠席しても大丈夫なものや、出席を取らない授業もあります。ですがそのような授業にも出席する中で学ぶこともあるでしょうし、出席点がない授業であっても、きちんと出席していれば自然とテスト前にも勉強する気が湧いてきます。毎回の授業内容を理解しておけば、テスト期間もずっと楽になります。「どれだけ夜更かしして遊んだとしても、授業は極力休まない」ように、自分に負けず頑張ってください。
② パソコン操作に慣れるべし!
最近の中学生や高校生は、スマートフォンの普及や学校から支給されるパソコンなどの影響もあり、パソコン操作をあまり苦とはしないようにも思いますが、大学生活では「レポート」や「プレゼンテーション」、そして「論文」の作成が欠かせないスキルとなります。
まずはパソコンの基本操作(Word、PowerPoint、Google ドキュメントなど)を使いこなせるようにしておくのがおすすめなのはもちろん、まずは早く正確にタイピングができるようになりましょう。私が大学生だった5~6年前は手書きのレポートが認められることも多かったですが、コロナ禍でオンライン授業やオンラインでの課題提出が増えてからはレポートの提出も手書きではなく、ワードなどの文書作成ソフトを使用して作成したものを提出するように求められることが増えたようです。
タイピングの練習としては寿司打などのタイピングゲームをやりこむことをお勧めします。私の場合、大学4年生の1年間がコロナ禍と重なり、翌年からの入社の準備をしておく必要もあり、一時期寿司打にかなり熱中していました。タイピング初心者には寿司打の3000円コースでも難しいかもしれませんが、10000円コースをクリアできるくらいまで練習しておけば、レポートの作成効率も抜群に上がると思います。
↓↓タイピングゲーム「寿司打」はこちらから↓↓
タイピングの練習に加えて、ネットで「大学 レポート 書き方」と検索して、今のうちから実際のレポートについてイメージを膨らませておくことも大いに役に立つと思います。
③ 履修登録と時間割の組み方を理解すべし!
大学の授業は「自分で選ぶ」スタイルです。履修登録の仕組みはややこしく感じるかもしれませんが、慣れれば自由度が高く、興味のあることに集中して学べます。
履修登録のやり方は大学ごとに異なると思いますので、「どの授業を取ればいいのか」「どれくらい単位が必要なのか」「楽単(らくたん:単位が取りやすい授業)の見分け方」など、先輩やSNSの情報も参考にして、戦略的に時間割を組んでみましょう。
新歓(新入生を歓迎するためのイベントや集まり)に積極的に参加することでこのあたりの情報も得られるはずですのでお勧めです。(詳しくは次回のブログにて)
④ 将来を見据えた“学びの目標”を考えてみるべし!
今すぐ将来の夢を決める必要はありませんが、「大学4年間をどう過ごしたいか」を考える時間はとても大切です。
たとえば、資格取得や留学、ゼミでの研究、インターンシップなど、やってみたいことが少しでもあるなら、それに向けた学部選び・授業選びを意識しておくと、軸のある大学生活になります。
また、大学での勉強は、1つのテーマを深くまで突き詰めていく勉強になります。上の学年に進級していくと、ゼミや研究室で研究するテーマを決めなくてはならなくなるので、その時までに自分が何を研究したいか考えておくとよいかと思います。
もちろん自分の興味のあることを楽しく勉強できるというのが一番ですので、面白そうだなと思う授業を選んで受講して、そこから自分が本当に勉強したいことややりたいことを探していくこともお勧めです。
今回は「学習面」から新大学生に伝えておきたいことをまとめてみました。
大学生としての期間は人生の夏休みと呼ばれるほど自由度の高いものですので、この期間にしかできないことをたくさん経験してほしいと思いますが、自分の勉強にもしっかり力を入れることでより魅力的な人になってほしいと思います。
先日の住之江校の合否報告のブログにも新高1生向けに似たようなことを書きましたが、大学に合格するということは高校生にとって大きな目標だったはずですが、ここで人生が終わるわけではありません。大学在学中も、卒業後も自分の置かれた環境で精一杯の努力をできる人こそ、その後の人生を切り開いていけるのだと思います。
次回は「私生活面」からアドバイスをまとめてみますので、是非そちらもご覧ください!
文責:小西正也