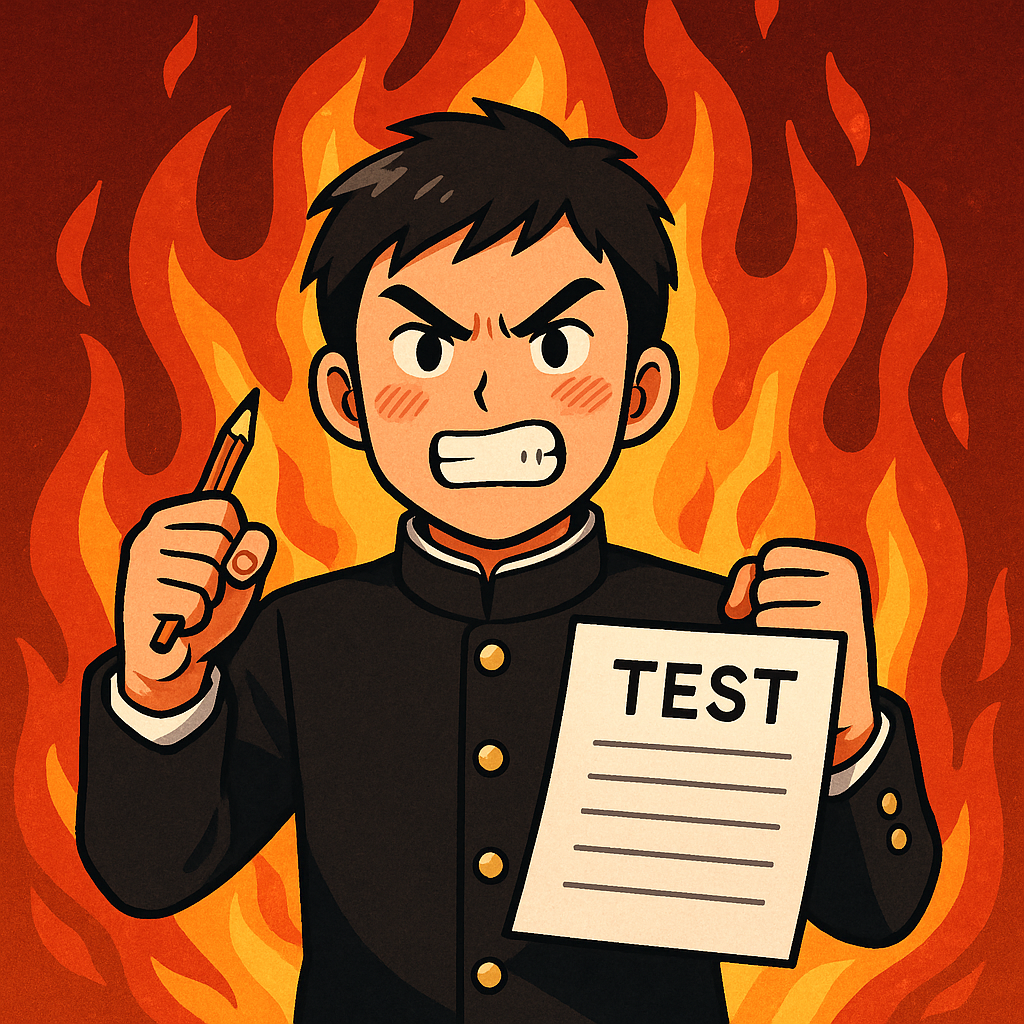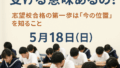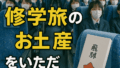── “本気モード”が塾に満ちる一週間
5月も半ばに差しかかり、中之島中学校の中間テストが目前に迫ってきました。
創心館でも先週から、中之島中の塾生たちが続々と塾にやって来て、普段以上に集中した空気で自習や復習に取り組む姿が見られています。
「今回は順位を上げたい」
「苦手科目で平均は超えたい」
「提出物も早めに終わらせて、しっかり準備したい」
そんな思いを胸に、部活や習い事の合間を縫って、限られた時間の中でも自分の課題に真っ直ぐ向き合おうとする姿が、本当に頼もしく映ります。
中間テストは、「本格的な内申の土台」が意識され始める最初の山場とも言えるタイミング。
だからこそ、生徒たちの表情や行動にも自然と“本気モード”のスイッチが入っているのです。
“熱血”モード、全開中!
創心館のテスト前恒例の取り組み、それが“熱血”です。
この期間は、ただ塾を開けて待っているだけではなく、原則全員が「自習に来て当たり前」という前提のもと、全員参加での学習強化週間として運営しています。
中之島中のテスト1週間前より、通常授業の有無にかかわらず、平日・休日ともに教室を開放しています。
生徒たちは、いつもより少し早く来てワークを進めたり、授業のない日でも自習のために来校したりと、まさに“やらざるを得ない環境”の中で、それぞれが黙々と勉強に取り組んでいます。
講師陣も、生徒が困っている単元を即座にフォローできるよう、質問対応体制を強化。
「英語の本文の意味がうろ覚えで…」という子には和訳チェックと音読を、「理科の計算が苦手で…」という子には式の作り方から丁寧にアドバイスを。
“わからない”を“できる”に変えるサイクルが、日々の中で回っているのを感じます。
夕方の教室に漂う静かな集中空間
特に印象的なのは、部活を終えた夕方の時間帯です。
少し疲れた表情で教室にやって来た生徒たちが、それぞれの席に着いてからは、言葉も少なめに淡々と課題に取り組んでいく。
その静けさの中に、確かな集中力と覚悟が漂っていて、教室全体が自然と引き締まった空気になります。
理科のプリントを繰り返し解き直す子。
英語の教科書本文を何度も音読して、単語や熟語を指でたどりながらチェックしている子。
国語の記述問題を何度も書き直して、先生と一緒に「どう書けば点がもらえるか」を確認している子。
「疲れていても、今日できることをひとつでも増やしたい」――そんな気持ちが、鉛筆の動きやノートに刻まれた字からひしひしと伝わってきます。
それぞれの“課題”に向かって、確かに手が動いている
教室を見渡すと、ページをめくる音、シャーペンの走る音だけが静かに響いています。
誰かがまとめノートを見直しながら、覚えた用語をノートの余白に何度も書き出している。
別の生徒は、過去問の計算問題に集中していて、答え合わせの後に赤ペンで「なぜ間違えたか」を自分なりの言葉で書き込んでいます。
社会の白地図を埋めている子、英語の本文をノートに写して暗唱している子、漢字を何度も丁寧に書き込んでいる子。
どの机にも、それぞれの課題にあわせたプリント・ノート・参考書が広がっていて、
“ただ塾に来ている”のではなく、「何をすべきかを自分で考えながら手を動かしている」という雰囲気に満ちています。
誰かの真剣な姿勢が、また別の誰かの背中を押す。
そんな良い連鎖が、教室のあちこちで静かに、でも確かに起きているのを感じます。
テスト勉強に「戦略」を
創心館では、「机に向かっている時間」も重要ですが、「中身の濃さ」「取り組み方の工夫」にも重点を置いてサポートしています。
生徒にとっては、「どこから手をつければいいか分からない」という迷いが、最初の大きな壁になります。
ある生徒は、理科のワークを何周もしているのに点数が伸びず、悩んでいました。
確認してみると、問題を解いて答え合わせをして終わり――という「やったつもり」状態になっていたのです。
そこで「基本事項の暗記→基本問題で確認→苦手な単元を集中演習」という順番を一緒に整理し、
さらに間違えた問題をノートにまとめて“やり直しノート”をつくるよう指導しました。
今では、本人の中に「どうすれば覚えられるか」「理解できるか」という意識が芽生え、勉強の姿勢そのものが変わってきています。
最後に
中之島中の中間テストまで、いよいよあと数日。
ここからの一歩一歩が、結果を大きく左右します。
創心館では、最後まで生徒たちに寄り添い、
「やってよかった」「自分で頑張れた」と思えるテスト期間になるよう、全力でサポートしていきます。
テスト勉強は、決して“楽しい”ことばかりではありません。
それでも、「昨日の自分より、少し前進した」――そんな実感を一つでも多く得られるよう、一緒に頑張っていきましょう!