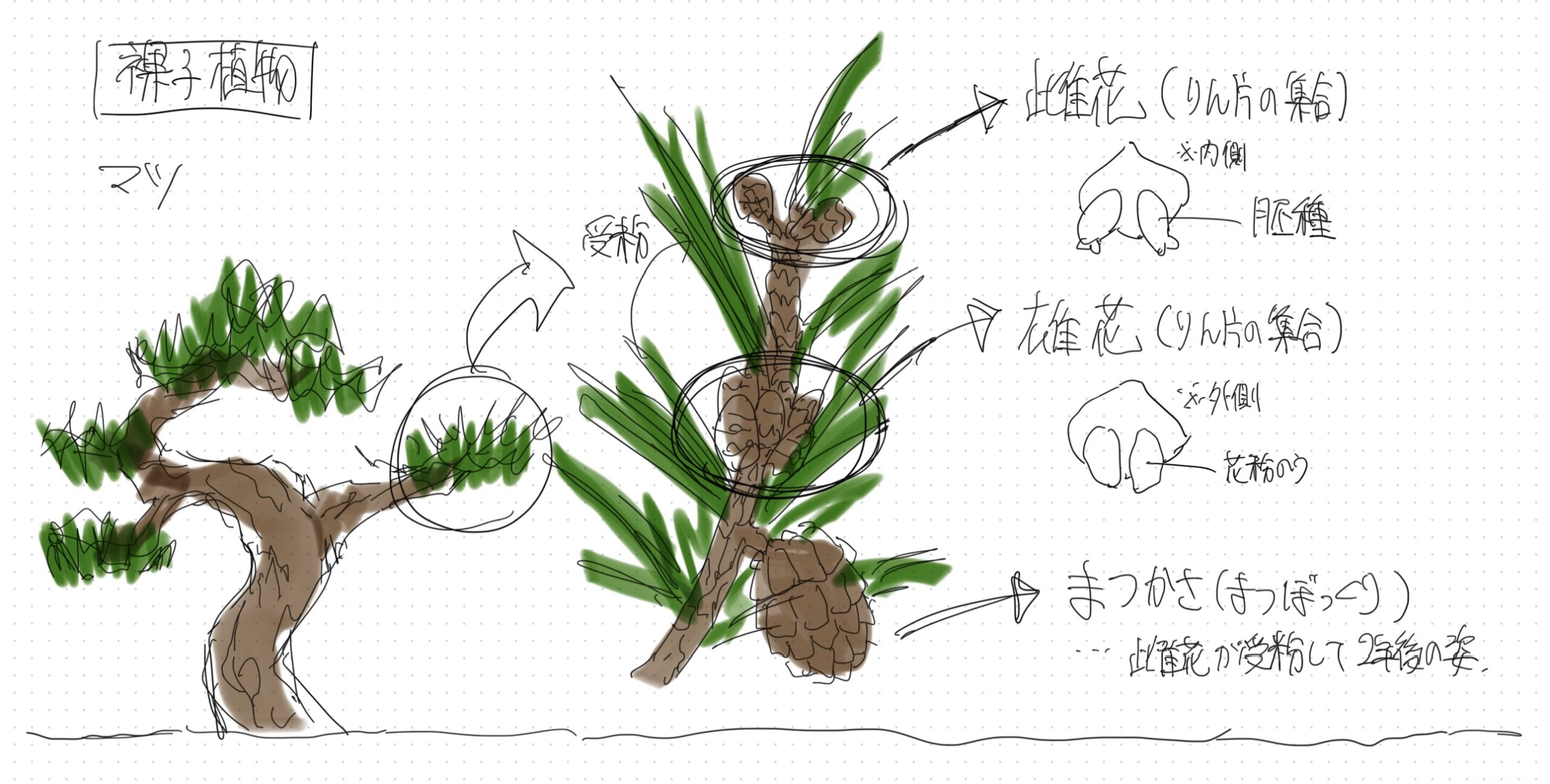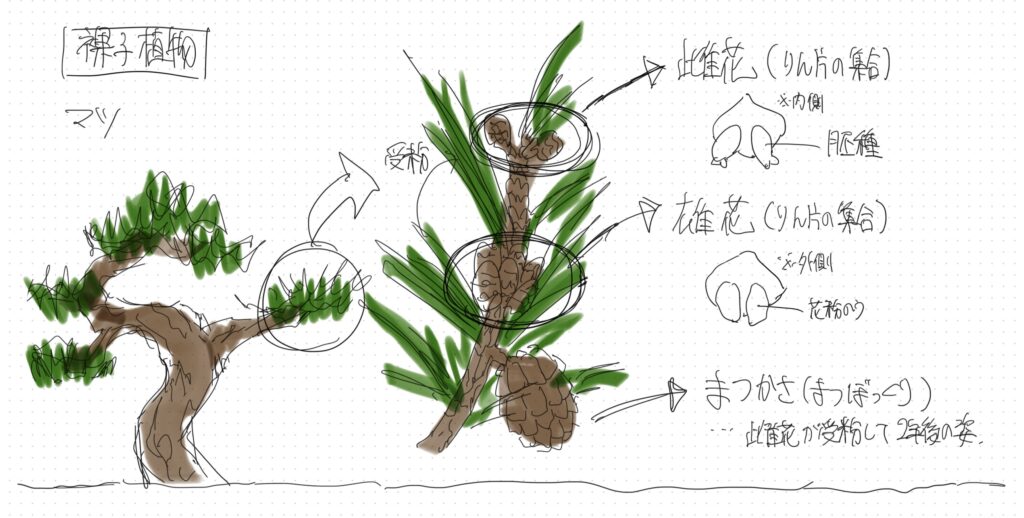
中1理科「裸子植物」の授業から
こんにちは。中学1年生の理科を担当している上原です。
「裸子植物(らししょくぶつ)」という言葉を初めて聞いたとき、多くの生徒は、「なんだか地味な植物?」という印象を持つようです。
たしかに、鮮やかな花びらもなく、果実もできません。
けれど、裸子植物は過酷な環境に適応しながら、何億年も生き延びてきた植物です。
今回の授業では、その代表である「マツ」を通して、花のつくりとそのはたらきについて学びました。
裸子植物とは、「タネがむき出し」の植物
植物には、タネをつくって増える種子植物(しゅししょくぶつ)と、タネをつくらない胞子植物があります。
そのうち、種子植物はさらに2種類に分けられます。
- 被子植物(ひししょくぶつ):タネが果実の中に包まれる(例:サクラ、アサガオ)
- 裸子植物(らししょくぶつ):タネが包まれず、むき出しで育つ(例:マツ、スギ)
めしべの中に**胚珠(はいしゅ)**があるのが被子植物、
胚珠が直接見えるようにあるのが裸子植物の大きな違いです。
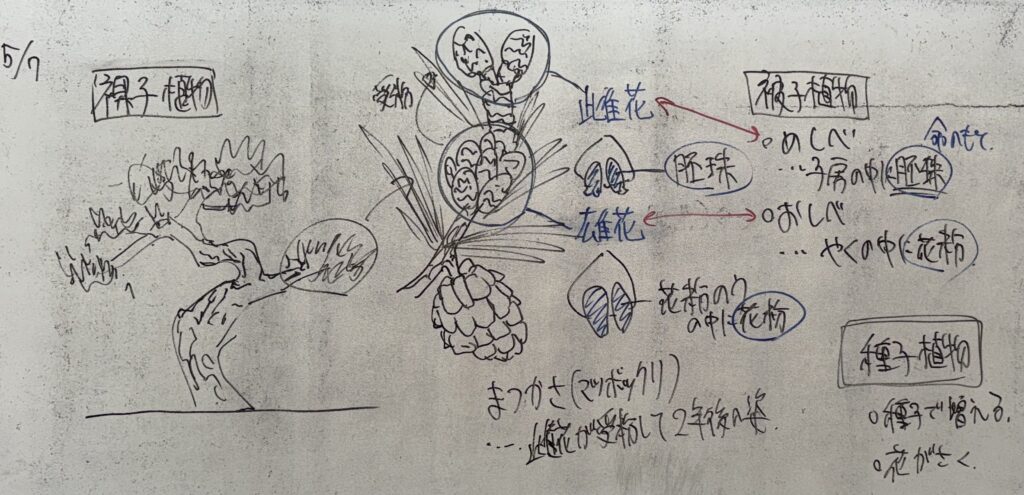
マツの“花”を観察してみると…
板書にもあるように、マツの木には次の2種類の「花」があります。
- 雄花(おばな):花粉をつくる
- 雌花(めばな):花粉を受け取り、タネをつくる準備をする
一見すると、どちらも“花”らしく見えません。
でもそれぞれの中には、ちゃんと「花粉のう」や「胚珠」といった器官があります。
つまり、マツには「花びらがない花」がついているのです。
松かさは、花のその後のすがた
板書の右下にも書かれているように、あの松ぼっくり(=まつかさ)は、 雌花が受粉してから2年後のすがたです。
春に飛んできた花粉が、雌花の胚珠に届いて受粉。
そこからじっくりと時間をかけてタネを育て、2年後に成熟します。
このゆっくりとした営みの中にも、植物の確かな“はたらき”があります。
花の見た目にとらわれない視点を
「花」と聞くと、どうしても華やかな形や色を思い浮かべてしまいます。
けれど、理科の授業ではその“見た目”ではなく、はたらきで見ることの大切さを学びます。
今回の授業では、
「タネをつくるには何が必要か」
「植物はどのように工夫しているのか」
という視点から、花のつくりを見直すことができました。
最後に:自然に目を向けてみよう
次に松ぼっくりを見かけたとき、ぜひ思い出してみてください。
「これは2年前の春、マツの雌花だったのか」と。
そう考えると、ふだん見慣れた景色も、少し違って見えるかもしれません。