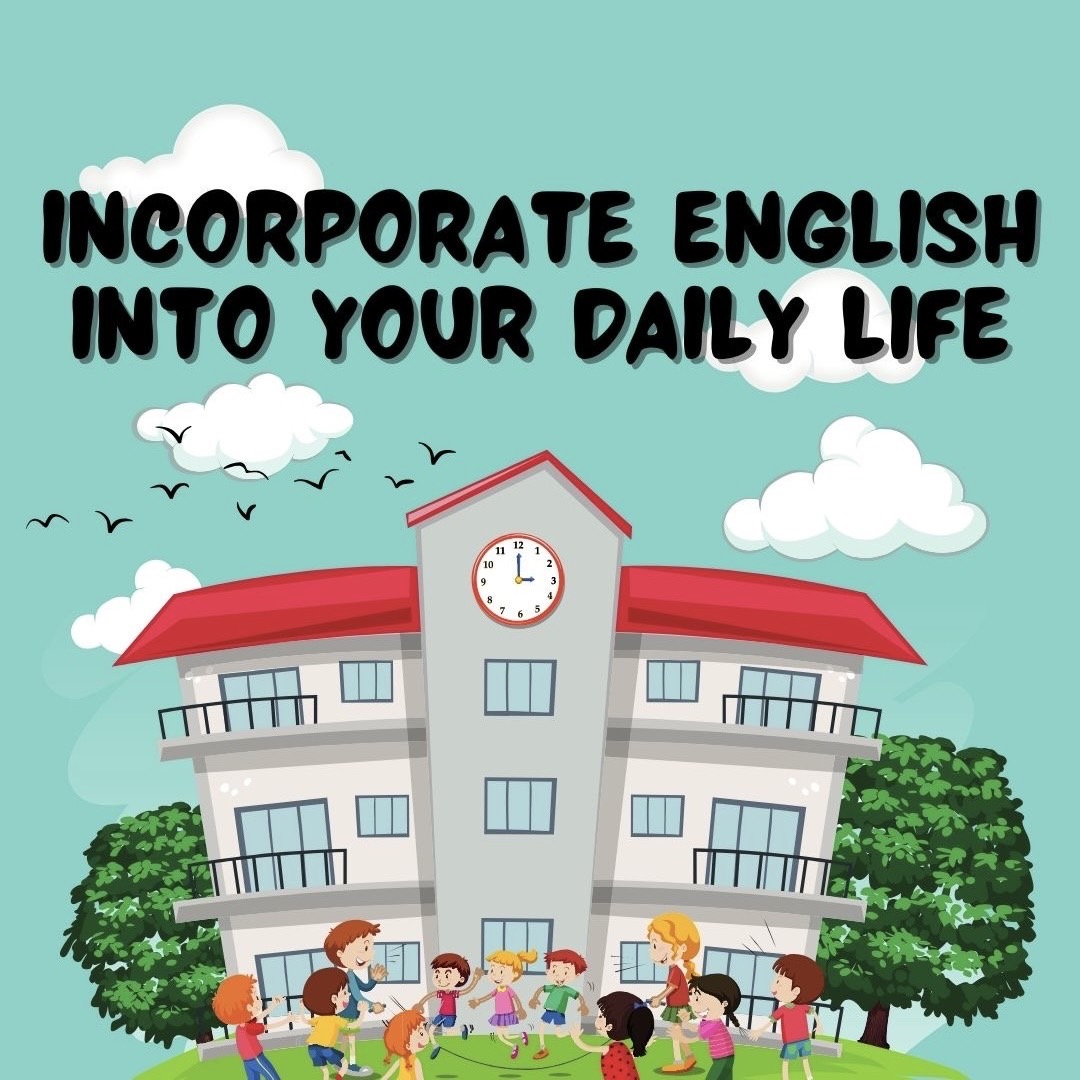まず初めに、2021年から教科書が大幅に改定になり、特に中学1年生の負担が大きくなったのは皆さんご存知の事かと思います。小学校で、ある程度英語を習っている前提で教科書が組み立てられています。ところがその前提の小学校の英語教育ですが、生徒たちに聞き取りをしますと小学校の先生によって、やっているレベルが大きく異なるようです。その流れで中1の英語に突入すると、多くの”英語脱落者”を生み出してしまうのではないかと危惧しております。ということで今回は小学生のうちにどよようにして英語に触れればいいのか考えてみたいと思います。
小学生と中学生で求められる能力の違い
小学校の英語とは?
「慣れ親しむ・興味をもつ」ために歌やゲームなどで英語が楽しい教科だと認識してもらい、英語に対する拒絶感をなくすことに重点をおいているといっていいでしょう。もちろん、授業内では簡単なフレーズや身近な英単語が中心になります。また、成績評価に関しても【どれだけ積極的に取り組んだか、関心があるか】を中心としています。
中学校の英語とは?
中学生になると読み、書き、文法の基礎を学び、本格的に囲碁を「学習」する段階に入ります。当然、授業内ではこれまでとは比べ物にならない単語量が必要となり、文法事項も学びます。さらに、評価基準については積極的に授業に取り組む姿勢は変わりませんが、定期テストが多くを占めます。

※旧学習指導要領:2020年度までのものを指します
中学1年生の1学期から重要文法事項が目白押し
中1の教科書のUNIT1に「be動詞」と「一般動詞」と「助動詞のCan」が出てきます。一昔前なら助動詞は2学期以降に習います。塾生たちはこの順番に英語のルールを学んでいたのですが、塾に通っていない生徒たちは非常に混乱するでしょう。be動詞と一般動詞の区別がなかなかつかない生徒が多い中、助動詞まで加わるのですから。be動詞が定着していないまま一般動詞に進むのはかなり危険ですが、それに加えて助動詞まで出てくると、もう何が何やら分かりません。中1の1学期で英語嫌いが続出する可能性も大いにあり得ます。
小学6年生の2学期から中学校の準備を
やはり、小学校と中学校の”英語のギャップ”を埋めるためには2学期頃から「読み・書き・文法」に力を入れていく必要があります。初めはアルファベットの大文字と小文字を必ず4本線を用いて書けるようにすることから始めるといいでしょう。そこから数字や季節、曜日・月(暦)など少しずつ難易度を調節するのが理想です。ここで大切なのはやはり【英語への拒絶感を無くす】ことです。
では具体的にどういったことをはじめればよいのでしょうか?
英語への拒絶感を無くす=日常に英語を取り入れる
1.「音」に親しむ時間をつくる
── 英語耳を育てる毎日できる5分習慣
英語は「音」が大切。リスニング力や発音の土台を小学生からしっかり育てることで、中学生になった際に「音」と「スペル」が結びつくようになります。
〈家庭でできること>
・毎日5分、英語の音声を聞く習慣をつけましょう(例:NHKの基礎英語、YouTubeの子ども向け英語チャンネルなど)。
・一緒に聞いた後、「この単語わかった?」など会話するだけでも効果的です。
2.「英語=暗記」ではなく「英語=使うもの」として学ぶ
── 日常に英語を取り入れる小さな工夫
英語はテストのための教科ではなく「伝えるためのツール」であることを、早い段階で伝えるのがカギ。
〈家庭でできること>
・冷蔵庫に「英単語ポストイット」を貼って、目に入るたびに英語に触れさせる
・夕食後に「今日の英単語クイズ」などゲーム感覚で言葉に触れる
3.「小さな成功体験」を積ませる
── モチベーションを上げるコツは“できた!”の積み重ね
最初の段階で英語に自信がつくと、その後の伸びが全く違います。
〈家庭でできること>
・「こんなに単語覚えたね!」「発音上手になったね!」と、小さな成果をこまめに褒める
・英検5級、4級などへのチャレンジもよい目標になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このように、英語は「教科」ではなく「ツール」であることを意識しながら、音・日常・成功体験の3つを組み合わせると、ぐっと前向きに取り組めるようになります。是非、試してみてください。
文責:藤田