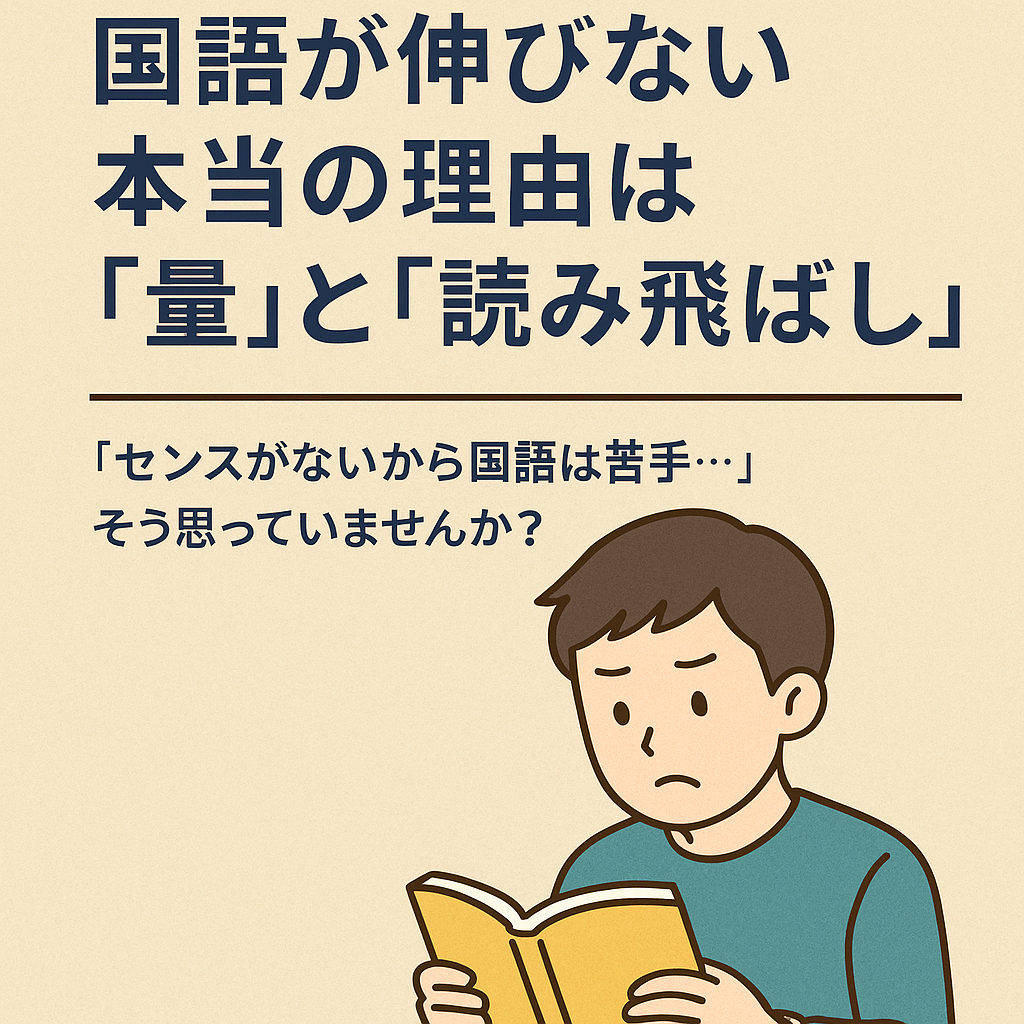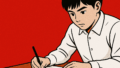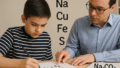「センスがないから国語は苦手…」そう思っていませんか?
たしかに、国語には“センス”がある人がいます。読むスピードが速く、筆者の考え方を自然に理解できるタイプです。
しかし、国語の点数を決めるのはセンスだけではありません。
読み方の技術と日々の積み重ねによって、苦手な人でも必ず伸ばすことができます。
センスの正体は「読み方の型」
センスがある人は、実は無意識のうちに「読み方の型」を使っています。
たとえば――
- 指示語が何を指すかを確認する
- 接続語で文の関係を整理する
- 筆者の主張と具体例を区別して読む
こうした“読み方のルール”を自然に身につけているのです。
でも、意識して練習すれば誰でもできるようになります。
つまり、センスは努力で再現できる力なのです。
読み飛ばさずに「止まって考える」
国語が苦手な人の共通点は、分からないところをそのままにして読むことです。
わからない言葉や表現が出てきたら、いったん立ち止まる習慣をつけましょう。
- 語句:意味をスマホや辞書で調べる
- 指示語:「それ」「この」などが何を指すか本文で確認する
- 接続語:「しかし」「だから」などの前後関係を整理する
この「ストップ&チェック」を繰り返すことで、文章全体のつながりが見えてきます。
“なんとなく読む”を卒業して、“理解して読む”に変えましょう。
分からない言葉を調べることが、センスを育てる
読解力の土台は語彙力です。語彙が足りないと、筆者の言いたいことがあいまいになってしまいます。
普段の会話やネット記事などで知らない言葉に出会ったときは、その場で調べましょう。
最近はスマホで意味をすぐに確認できます。
調べた語をメモアプリに残したり、ノートに書きためたりするだけでも効果的です。
1日3語でも、1年で1000語。
語彙を増やすことこそ、センスを磨く最短ルートです。
根拠をもって答えられるまで、時間をかけて解く
国語の答えは「なんとなく」では当たりません。本文中の根拠を見つけ、「なぜそうなるのか」を自分で説明できるまで粘りましょう。
答え合わせをするときは、次の2点を習慣にすると、読解の精度が一気に上がります。
- 根拠のある文を線で引く
- 間違った選択肢がなぜ違うか考える
「毎日コツコツ」で基礎を固める
中学生でも、短文教材からやり直すのは非常に有効です。文の構造がシンプルで、“読み方の型”を身につけやすいからです。
また、国語は一夜漬けでは上がりません。
1日15〜20分、毎日1題を解く習慣が力になります。
少しずつでも「読む量」を増やすことが、センスの差を埋める最短の道です。
まとめ:センス+努力=本当の国語力
国語は、センスがある人が有利に見えます。
でも、センスがない人も正しい勉強法で“読むセンス”を養い、点数を伸ばすことができます。
読み方を学び、語彙を増やし、根拠を持って答える――。
その積み重ねが、真の読解力をつくります。
センスがなくても、努力で追いつける。
センスがある人も、努力でさらに磨ける。
国語は、“センス×習慣”の掛け算で伸びる教科です。