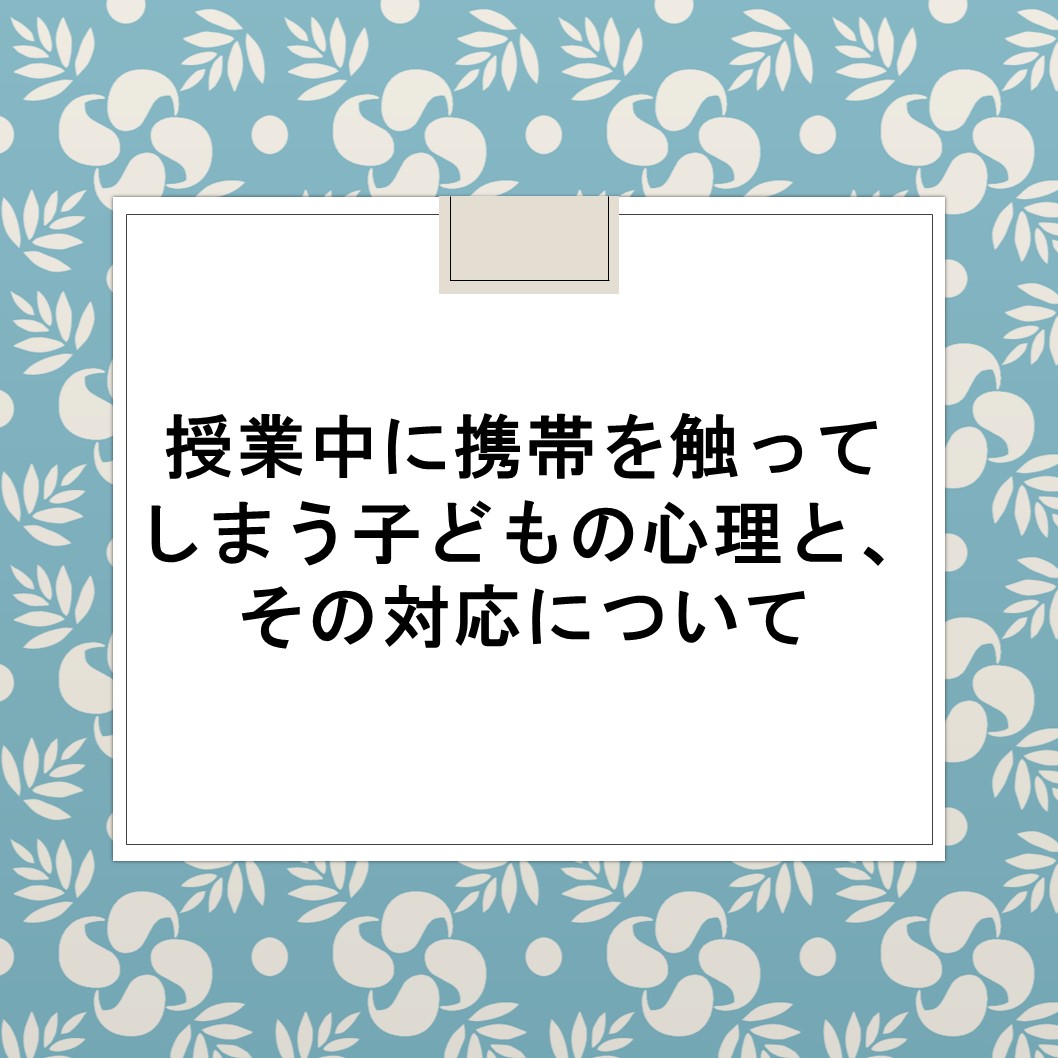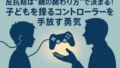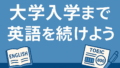近年、授業中に携帯電話を触ってしまう生徒は少なくありません。小学校や中学校に持っていき問題にもなっているようです。携帯は学習の妨げになるだけでなく、周囲の集中力にも影響します。本記事では、塾としての指導方針と、なぜ子どもたちは注意されてもスマホに手を伸ばしてしまうのか、その心理面について考えてみます。
子どもが授業中に携帯を触ってしまう心理
習慣依存
家でも常に触っているため、無意識に手が伸びてしまいます。SNSやゲーム、動画など「ちょっとだけ」のつもりが気づけば時間を奪われるのは大人でも同じ。子どもにとっては誘惑を断ち切るのはさらに難しいことです。
ルールを軽く見ている
「少しくらいなら大丈夫」「本気で叱られないだろう」という気持ちもあります。過去に注意されても、その場しのぎで済んできた経験があると、本人の中で「結局許される」という甘さにつながってしまいます。
境界を試す行動
スマホに限らず、「先生は本気で叱るのか?」「他の先生なら違うか?」と探りを入れる行動をとる場合があります。いわゆる「境界を試す」行動であり、大人から見れば些細な挑戦ですが、子どもにとっては成長の一部でもあります。
「バレなければOK」という感覚
スマホは手軽に隠せるため、「見つからなければ問題ない」と考えてしまうケースもあります。規律より損得勘定で行動しているわけです。短期的には本人に得があるように見えても、結局は学習の妨げとなり、損をしているのですが、それを理解するのはまだ難しい段階です。
現実逃避
授業が難しい、勉強に不安があるとき、気持ちを紛らわすためにスマホへ逃げることもあります。スマホに触れている間は「分からない」という現実を直視せずに済むからです。
承認欲求
少数ですが、注意されることで「自分に注目してもらえる」と感じる子もいます。存在感を示すための行動が、結果として授業の妨げになることもあります。
創心館の指導方針 ― 「授業中は携帯に触れない」
塾としては、ルールをシンプルに、そして例外なく徹底することが大切です。
ルールはシンプルに
授業中は机に出さない、カバンにしまう。これだけを徹底します。複雑なルールにせず、明確で誰もが理解できる基準を設けます。
一貫した対応で例外を作らない
どの講師でも同じ基準で注意します。「今日はいいか」をなくし、全員同じルールで公平に扱います。この先生なら許してくれる、という例外を作らないことが信頼感につなげていきます。
参加型の授業にする
子どもたちが受け身にならないよう、小テストや質問を挟み、5〜10分ごとに切り替えを意識します。集中が途切れる前に流れを変えることで、「スマホに逃げる余地」を減らすのです。
塾と家庭の連携で信頼を高める
何度か注意した後にルールを守れない場合は「習慣改善に向けて指導中」であることをご家庭に共有します。
塾と家庭で一貫した姿勢を示すことで、生徒は「本当に触れない環境だ」と理解してもらいます。
まとめ
スマホに手が伸びる背景には、依存や習慣、境界を試す気持ち、現実逃避など、さまざまな心理があります。それを「やる気がないから」と片付けてしまうと、本質を見誤ってしまいます。
創心館では、「授業中は携帯に触れない」というシンプルで一貫したルールを守り、参加型の授業で子どもたちの集中を引き出すことを心がけています。ルールを守ることで得られるのは、静かな教室だけではなく、「勉強に集中できる環境」という何よりの財産です。
保護者の皆さまにもご家庭でのサポートをお願いできればと思います。授業外でのスマホとの付き合い方を一緒に考え、子どもたちが本来の学びに集中できるよう、これからも取り組んでまいります。