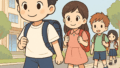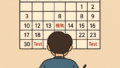先日、中学3年生の塾生と一緒に「チャレンジテスト」の過去問(数学)に取り組みました。チャレンジテストと聞くと、特別に難しい問題が並んでいるように感じる人も多いと思います。しかし実際に解いてみると、数学に関しては「普段の実力テストと大きな違いはない」ということが分かりました。今回は、その時の様子や気づきをまとめたいと思います。
チャレンジテストとは?
大阪の公立中学校に通う生徒にはおなじみのテストですが、あらためて説明すると、チャレンジテストは大阪府教育委員会が実施する学力調査です。定期テストのように学校ごとに問題が異なるのではなく、府下一斉に同じ問題が出題されるのが特徴です。
実施時期や科目数は学年によって異なります。
- 1年生 … 冬休み明けに実施。英語・数学・国語の3科目
- 2年生 … 冬休み明けに実施。英語・数学・国語・理科・社会の5科目
- 3年生 … 2学期が始まってすぐに実施。英語・数学・国語・理科・社会の5科目
「模試」と呼ぶほど受験色は強くありませんが、自分の学力を客観的に把握できる大切な機会です。
実際に解いてみた感想
今回、生徒と一緒に数学の過去問を解いてみました。最初は「難しそう…」と言っておりましたが、問題に向き合うと「定期テストで似た問題をやったことがある」と気づく場面が多くありました。
出題の中心は、計算力、文章題の理解、図形の基礎など、中学校で学ぶ内容の定着を確認する問題です。確かに文章が少し長めだったり、問い方に工夫があったりしますが、根本的には普段の実力テストと大きな差はありません。
要するに、数学のチャレンジテストに関しては、特別な「チャレンジテスト用の勉強」をしなくても、日頃の学習をしっかり積み重ねていれば十分に対応できる内容です。
生徒の反応
一緒に解き進めていく中で、「思ったより解ける」「実力テストと変わらないんだ」と感じてくれたはずです。最初に抱いていた不安や緊張が、実際に取り組むことで和らいでいく様子が印象的でした。
また、普段の授業で練習している基礎計算や文章題の解き方がそのまま活かせる場面が多く、「やってきたことは無駄ではなかった」と実感できたことも良い収穫だったようです。
塾としても、このように一緒に取り組むことで、生徒たちが安心感を持ち、次のテストに前向きな気持ちで挑戦できることを大切にしています。
これからの勉強のポイント
チャレンジテストに特別な対策は不要とはいえ、普段の学習の取り組み方が何より重要です。
- 計算問題は「正確さ」と「スピード」を意識する
- 文章題は問題文を丁寧に読み取り、式に落とし込む練習をする
- 図形は基本の性質や定理を理解し、自在に使えるようにする
これらはチャレンジテストだけでなく、実力テストや高校入試にも直結する力です。チャレンジテストをきっかけに自分の得意・不得意を見直し、日々の勉強につなげていくことが大切です。
おわりに
「チャレンジテストは特別に難しいもの」というイメージを持つ人も少なくありません。ですが、実際に解いてみると「実力テストと大きな違いはない」と気づくはずです。むしろ、普段の学習を大切にしている人にとっては、自信を深める機会にもなります。
創心館では、今後も過去問演習を通じて、生徒が安心してテストに臨めるようサポートしていきます。特別な勉強法よりも、日々の積み重ねこそが最良の準備です。チャレンジテストを恐れず、普段の学習の成果をしっかり発揮してほしいと思います。