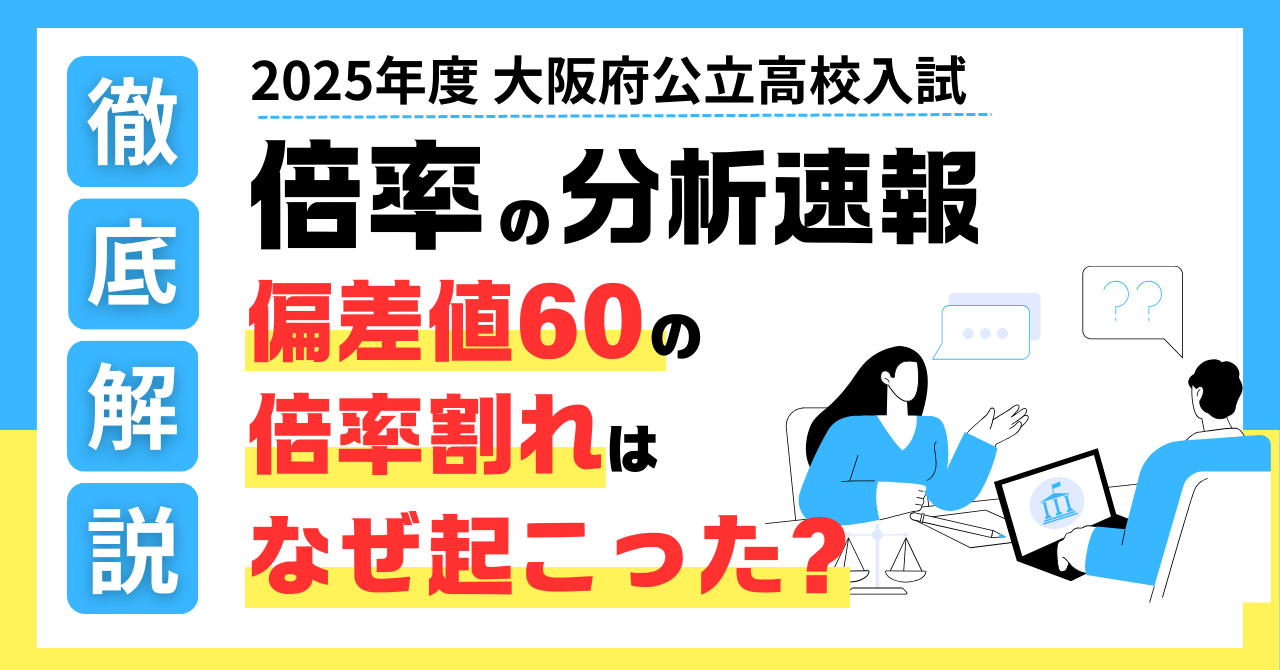【序論】2025年度 大阪府公立高校入試の異変とは?
2025年度の大阪府公立高校入試において、例年とは異なる異変が発生しました。偏差値60以上の公立高校でも定員割れが複数発生し、従来の受験市場の常識が崩れつつあります。
まずは以下の表をご覧ください。
高校名を偏差値順に並べ、さらにその横に今回の倍率を併記しました。
偏差値 高校名 倍率
75 北野 1.27
74 天王寺 1.21
73 三国丘 1.31
72 大手前 1.19
72 茨木 1.36
70 高津 1.29
70 豊中 1.49
69 四條畷 1.44
69 生野 1.26
69 岸和田 1.18
68 春日丘 1.46
68 寝屋川 0.94
67 泉陽 1.32
67 千里 1.34
67 千里 1.34
66 箕面 1.09
66 和泉 1.11
65 住吉 1.26
63 清水谷 1.22
63 池田 1.19
63 三島 1.21
63 八尾 0.99
63 富田林 1.06
63 和泉 1.11
63 東 1.18
62 箕面 1.09
62 今宮 1.19
61 夕陽丘 1.23
61 桜塚 1.20
61 北千里 1.20
61 東 1.18
60 東住吉 1.13
60 牧野 1.16
60 いちりつ 0.93
60 鳳 0.94
60 泉北 1.04
60 泉北 1.04
59 夕陽丘 1.23
59 山田 1.36
59 佐野 1.03
59 東 1.18
59 市岡 1.21
58 刀根山 1.17
58 佐野 1.03
57 旭 1.24
57 布施 1.10
57 槻の木 0.80
56 枚方 1.08
56 登美丘 1.04
55 阿倍野 1.07
55 花園 1.13
55 河南 1.00
55 久米田 1.15
55 堺東 1.01
54 香里丘 0.96
54 狭山 1.05
54 大阪ビジネスフロンティア 1.09
54 千里青雲 0.83
53 旭 1.24
53 高槻北 0.97
53 花園 1.13
53 山本 1.17
53 桜和 1.31
52 阪南 1.05
52 吹田東 1.31
52 都島工業 0.94
52 芦間 1.03
51 高石 0.92
51 日根野 0.97
51 咲くやこの花 1.09
50 豊島 0.91
50 芥川 0.93
50 交野 0.69
50 金岡 1.00
50 柴島 1.24
―――偏差値50のライン―――
49 摂津 1.01
48 門真なみはや 0.95
48 みどり清朋 1.02
48 金剛 1.02
48 長野 0.66
48 岸和田市立産業 0.98
47 東淀川 1.22
47 港 1.08
47 藤井寺 1.03
47 桜宮 0.88
47 堺市立堺 0.99
46 渋谷 0.97
46 北かわち皐が丘 0.90
46 長尾 0.63
46 八尾翠翔 0.96
46 東百舌鳥 0.98
46 淀川工 0.84
45 茨木西 1.02
45 大冠 0.94
45 堺西 0.88
45 貝塚南 1.00
45 汎愛 1.01
45 大阪府教育センター附属 0.99
45 今宮工 0.93
45 貝塚 1.02
44 枚方津田 0.92
44 枚方なぎさ 0.86
44 農芸 1.02
43 緑風冠 0.92
43 泉大津 0.88
43 東大阪市立日新 0.88
43 八尾北 0.93
43 松原 0.97
42 吹田 0.94
42 阿武野 0.90
42 大塚 0.77
42 福井 0.50
41 守口東 1.02
41 堺上 0.88
41 淀商業 0.90
41 佐野工 1.00
40 北摂つばさ 0.66
40 伯太 0.98
40 鶴見商業 0.81
40 園芸 0.83
40 東住吉総合 0.81
上の偏差値は以下のサイトを参照しています。

※通常、創心館内部では五ツ木模試の偏差値を利用していますが、ここでは一般の方も参照できる上記のサイトの偏差値を利用して続きを書いていきます。
※複数の学科を持つ高校もありますが、便宜上、ひとつにまとめています。それぞれの学科の偏差値・倍率を知りたい場合は各自でお調べください。
これまで、大阪府の公立高校入試では、偏差値50を境に倍率の傾向が変わるとされてきました。一般的に、偏差値50以上の高校では志願者が集まり、倍率が1.0を超えることがほとんどでした。特に偏差値60以上の高校は、安定した人気を誇り、定員割れを起こすことは稀でした。
しかし、2025年度の入試ではこの「偏差値60以上なら倍率が発生する」という法則が崩れ、寝屋川高校(偏差値68)、八尾高校(偏差値63)、鳳高校(偏差値60)などの高校で定員割れが発生しました。これらの高校は、進学実績もあり、かつては倍率1.0を下回ることがなかった高校です。この状況は、大阪府の公立高校入試において、異例の事態といえます。
では、この現象は一時的なものでしょうか? それとも、受験市場の構造そのものが変化しつつあるのでしょうか?
このブログでは、私立高校の台頭、トップ校と二番手校の関係、受験生の志向変化、地域ごとの進学傾向など、多角的な視点からこの異変を分析し、今後の受験市場がどう変化していくのかを考察していきます。
【私立高校の台頭】公立高校離れはなぜ進んでいるのか?
かつて大阪府では、「公立高校に進学するのが当たり前」という文化が根強く、特に偏差値50以上の公立高校は安定した人気を誇っていました。しかし、近年は公立高校離れが進み、私立高校の人気が高まっている傾向が見られます。その背景には、以下の3つの要因が考えられます。
① 私立高校無償化制度の影響で、私立進学のハードルが低下
大阪府では、私立高校の授業料無償化制度が拡充されており、世帯収入に関係なく、多くの家庭が私立高校を選択できるようになりました。
従来、私立高校は学費の負担が大きいため、経済的な理由から公立高校を選択するケースが多くありました。しかし、無償化制度の拡大により、「学費の心配をせずに、進学実績の良い私立高校を選ぶ」という選択が可能になったのです。
例えば、授業料が年間50~60万円かかる私立高校でも、無償化制度により実質負担がゼロになり、「公立高校と費用面での差がなくなった」ことが、公立離れを加速させていると考えられます。
※しかし依然として私立高校では授業料以外での費用が多くかかるというのも事実です。この件に関しては機会を改めて書こうと思います。
② 特待生制度・進学サポートの充実で、私立高校の魅力が増している
私立高校は、近年、学力上位層の生徒を確保するために特待生制度を強化しています。
例えば、
- 成績上位者は授業料の一部または全額免除
- 入試の成績に応じた特待制度(特待A・B・Cなどのランク分け)
- 大学進学を視野に入れた個別指導・推薦枠の充実
といった施策を導入することで、「偏差値60前後の公立高校に進むよりも、手厚い支援のある私立高校を選ぶ」という選択肢が広がっています。
また、指定校推薦の枠を多く持つ私立高校の方が、大学受験で有利に働く可能性があるという点も、公立離れを加速させている要因の一つです。
③ ICT教育・学習環境の充実で、公立高校との差が拡大
私立高校は、公立高校と比較して、ICT教育や学習環境の整備に積極的です。
例えば、
- 全生徒にタブレット端末を配布し、オンライン学習を強化
- 大学受験対策としてAI学習システムを導入
- 個別最適化された学習カリキュラムを提供
といった取り組みが進んでおり、「学習環境の充実度」で私立高校が公立高校を上回るケースが増えています。
特に、コロナ禍以降はオンライン授業の有無が学校選びの重要なポイントとなっており、「ICT環境が充実した私立高校の方が安心して学べる」と考える家庭も増えています。
公立 vs. 私立の受験構造は変わりつつある
これまでは、「公立高校に行くのが一般的で、私立は滑り止め」という構図が主流でした。しかし、現在は以下のような変化が起きています。
| 過去の受験構造 | 現在の受験構造 |
|---|---|
| 公立高校が第一志望、私立は併願 | 最初から私立専願を選ぶ生徒が増加 |
| 偏差値60前後の公立高校は安定した人気 | 公立二番手校を選ぶより、手厚い私立を選択 |
| 費用面の差が大きく、私立は裕福な家庭向け | 無償化で学費のハードルが下がり、誰でも選べるように |
この結果、「偏差値60以上の公立高校が必ずしも安定した志願者を確保できなくなっている」のが2025年度入試の特徴の一つです。
では、この変化はどの高校にどのような影響を与えたのでしょうか?
次のセクションでは、今年の異変として「偏差値60以上の公立高校が定員割れを起こした」ことを具体的に掘り下げていきます。
【トップ校 vs. 二番手校】文理科10校は安泰だが、二番手校の志願者が減少?
大阪府の公立高校入試において、最上位層が目指すのは「文理学科」 です。文理学科を設置しているトップ校10校(北野・茨木・天王寺・大手前・三国丘・高津・豊中・四條畷・生野・岸和田) は、2025年度も安定した倍率を維持しています。
文理学科のある高校は、大阪府全体の中で「絶対に合格したい」と考える生徒が集まるため、倍率が落ちにくい傾向にあります。特に、北野や天王寺、茨木といったトップクラスの文理学科は、今年も比較的高い倍率を維持しています。
しかし、文理学科にギリギリ届かない層の動向が変化 しています。
これまでなら「文理学科は難しいが、それに次ぐ公立の進学校を目指す」という流れが一般的でした。しかし、2025年度は「二番手校に行くくらいなら、最初から私立専願にする」という選択をする生徒が増えているのではないか?と考えられます。
「公立二番手校」から「私立専願」へのシフト?
文理学科に届かなかった層が、これまで進んでいたのが以下のような「公立二番手校」でした。
- 北野・茨木志望だった層 → 豊中・千里・春日丘・三島 へ
- 天王寺・高津志望だった層 → 八尾・清水谷・夕陽丘 へ
- 三国丘志望だった層 → 鳳・泉北 へ
- 四條畷志望だった層 → 寝屋川・牧野 へ
しかし、2025年度はこれらの高校の一部で定員割れが発生しました。特に寝屋川・八尾・鳳の3校は、以前は一定の倍率があったにも関わらず、今年度は定員を割る事態となっています(鳳高校は2年連続)。
(※春日丘は毎年倍率が高いですがなぜかご存知の方がいらっしゃったら教えてください!)
では、なぜこうした公立二番手校が敬遠されているのでしょうか?
「公立二番手校 vs. 私立専願」受験生の意識変化
- 「二番手校に進むなら、最初から手厚い私立を選んだほうがよい」
- 公立二番手校は進学校ではあるものの、私立高校のような特別なカリキュラムがない。
- それならば、「私立の進学コースで手厚いサポートを受けたほうが、大学受験に有利では?」と考える生徒が増えている。
- 例:大阪桐蔭・清風・明星・四天王寺・桃山学院などの私立進学校に流れるケース。
- 「特待生制度があるなら、私立の方がコスパがいい」
- 私立高校無償化制度の拡充で、特待生に選ばれれば実質無料で進学できる私立高校が増えた。
- 例えば、「二番手公立に行くなら、特待生枠で授業料が無料になる私立進学校のほうがよい」という選択肢が現実的になっている。
- 「学校の設備や学習環境の違い」
- 私立高校はICT教育・自習室の充実・指定校推薦枠の多さなど、学習環境が整っている。
- 一方で、公立二番手校は、「公立ならではの自由な雰囲気はあるが、大学の進学実績としては私立に劣る部分がある」と感じる受験生も増えている。
「文理学科ならチャレンジ、でも二番手なら私立」の傾向が強まる
このように、偏差値が高くても「中途半端な立ち位置」になりつつある公立二番手校は、受験生の選択肢から外れるケースが増えていると考えられます。
特に、「文理学科ならチャレンジするが、そこに届かなければ私立」という受験戦略が定着しつつある可能性があります。
実際に創心館でも最後の最後まで文理科にチャレンジするか、私立専願に切り替えるかを迷っていた生徒がいました。結局その生徒は私立専願でトップレベルの私立高校への進学を決めました。
では、こうした動きはどのように進んでいるのでしょうか?
次のセクションでは、「大手塾が四條畷に突っ込ませているのではないか?」という視点から、具体的な動きを考察していきます。
【推測】大手塾がむりやり四條畷を受けさせている?
今回の公立高校入試における寝屋川高校の定員割れは、これまでの傾向と比較すると異例の出来事です。従来、文理学科には届かないが、それに次ぐ進学校を目指す層が一定数おり、寝屋川高校や八尾高校は安定した志願者数を確保していました。しかし、2025年度は寝屋川高校で定員割れが発生しています。
この原因の一つとして、「大手塾が四條畷高校に無理にチャレンジさせている可能性がある」という推測が成り立ちます。
※この章は完全に筆者の安延個人の見解を書いています。完全に推測で書いていますので、事実と異なる部分があればご指摘ください。
大手塾は「文理学科の合格実績」を重視する
大手塾の基本戦略として、できるだけ多くの生徒を文理学科に合格させ、進学実績を積み上げることが重要視されます。文理学科は大阪府公立高校の中で最上位に位置付けられ、その合格実績が塾のブランド価値を高める要素となるためです。
この結果、以下のような受験戦略が広がっているのではないでしょうか。
- 以前なら → 「文理学科は厳しいからランクを下げて寝屋川高校へ」
- 最近は → 「ダメ元でも文理学科(四條畷)にチャレンジ」
過去には、大手塾が大阪南部で勢力を拡大する際に、三国丘高校に積極的に受験生を送り込み、数年間倍率が高止まりする現象が発生しました。当時の準大手塾が三国丘の合格実績を持っていたため、大手塾はこれを奪うために多くの受験生を三国丘受験へ誘導。結果として倍率が急上昇しました。その後、大手塾が三国丘の合格実績1位を獲得し、戦略的な目標を達成したことで、徐々に倍率が落ち着くようになりました。
この事例と類似する動きが、現在、四條畷高校で発生しているのではないか? というのが今回の推測です。
「公立二番手校よりも、まずは文理科を受けさせる」戦略?
大手塾では、「公立高校に合格することがゴール」ではなく、できるだけ上位の高校に合格させることで評価される 傾向があります。そのため、「少しでも可能性があるなら文理学科を受けさせる」という方針を取ることが多いと考えられます。
大手塾が「文理学科の合格実績を増やしたい」と考え、ギリギリの層にも四條畷受験を促している可能性があるのではないでしょうか。
これによって、本来なら寝屋川高校を受験していた層が、
「チャレンジ枠として四條畷高校へシフト」 → 「結果的に寝屋川高校の志願者が減少し、定員割れにつながった」 という流れが生まれた可能性があります。
「四條畷に届かないなら私立専願へ」?
さらに、近年の受験傾向として、「公立二番手校に行くよりも、手厚いサポートが受けられる私立高校を選ぶ」 という流れが強まっています。
大手塾が四條畷高校を強く推すことで、
✅ 合格した生徒は「チャレンジ成功」で四條畷へ進学
✅ 不合格だった生徒は「無償化なので滑り止めの私立へ進学」
という動きが生まれ、「四條畷に届かないならば寝屋川に出願」という流れが弱まっている可能性も考えられます。
この推測は正しいのか?
もちろん、これはあくまで安延個人の推測の域を出ない話です。
- 大手塾の戦略が本当に受験生の動向に影響を与えているのか?
- そもそも塾の指導だけで志望校がここまで偏るのか?
といった点については、何らかの事実を根拠としているわけではなく、まったくの推測の域を出ません。
しかし、過去の三国丘高校の事例を考えると、「大手塾の戦略によって、公立高校の倍率が変動する」 という現象が実際に起きる可能性は十分考えられます。
いずれにせよ、今回の寝屋川高校の定員割れが「偶然の出来事」なのか、「受験市場全体の構造変化を示す兆候」なのかを見極めることは重要です。
次のセクションでは、受験生の志向変化がどのように影響しているのか? について、さらに深掘りしていきます。
【受験生の志向変化】なぜ上位公立高校が敬遠されるのか?
かつて大阪府の受験生にとって、公立高校は第一志望として「当然の選択肢」でした。しかし、2025年度の公立高校入試では、偏差値60前後の公立高校の志願者が減少し、一部の高校では定員割れが発生する事態となりました。
その背景には、受験生の志向の変化があると考えられます。
以前は、「公立トップ校に届かなければ、二番手校を選ぶ」という流れが一般的でしたが、現在は「公立二番手よりも、手厚い私立の専願を選ぶ」という選択肢が主流になりつつあります。
では、なぜこのような変化が起こっているのでしょうか?
① 大阪府の公立高校入試はチャレンジ志向
大阪府の公立高校入試は、基本的に1校のみ受験可能であり、不合格になった場合は、滑り止めとして確保していた私立高校へ進学する仕組みになっています。
このため、従来の受験生は 「公立高校を受験するなら、絶対に合格しなければならない」 というプレッシャーを抱えていました。
従来なら、
✅ 「トップ公立に届かないなら、二番手公立にランクを下げる」
という意識がありましたが、現在の受験生は次のように考える傾向が強まっているようです。
✅ 「公立が不合格なら、私立でいいじゃない。だってどちらも無償なのだから」
このように、私立の上位校に合格しておけば、公立で失敗しても金銭的な負担は変わらず通えるという考えが広がっている可能性があります。
② 「公立トップ校 vs. 私立上位校」どちらを選ぶか?
私立高校の授業料無償化が進んだことで、
✅ 「公立に落ちたら私立」ではなく、「最初から私立でもいいのでは?」
という選択肢も現実的になっています。
例えば、以下のような戦略を取る受験生が増えています。
- 第一志望:北野・茨木・天王寺(文理学科)
- 私立上位校を確保(大阪桐蔭・清風・明星・四天王寺・関大一高 など)
- 公立がダメでも、私立上位校で問題なし!
この考え方が定着しつつあるため、「トップ校に合格できないなら、公立二番手校にランクを下げるのではなく、最初から私立専願にする」 という流れが生まれています。
③ 二番手公立高校は「中途半端な選択肢」になりつつある?
偏差値60前後の公立高校は、進学実績こそあるものの、
✅ トップ公立ほどのブランド力はない
✅ 私立進学校ほどの進学サポートはない
という状況にあり、受験生の選択肢から外れやすくなっています。
かつては、
✅ 「公立高校なら学費が安いし、進学実績もそこそこ良い」
✅ 「公立トップ校に落ちたら、二番手校でも仕方ない」
という考えが一般的でした。
しかし、現在は
✅ 「私立の上位コースの方が大学受験に有利かもしれない」
✅ 「特待生枠があるなら、学費面でも公立と変わらない」
✅ 「公立は一発勝負だから、リスク回避のために最初から私立を確保しよう」
という意識が強まり、二番手公立高校の魅力が相対的に低下していると考えられます。
④ 公立受験が「ハイリスク」になり、受験生の安全志向が強まる
また、少子化の影響もあり、受験生がより安全な進路を選ぼうとする傾向が強まっていると考えられます。
✅ 「公立高校は倍率が変動するので、合格ラインが読みづらい」
✅ 「公立受験は一発勝負なので、落ちたら強制的に私立に行くことになる」
✅ 「それなら、最初から私立の上位校を受けておけば安心」
このように考える家庭が増えていることも、公立高校離れを加速させる一因となっている可能性があります。
今後、偏差値60前後の公立高校はどうなるのか?
このような流れが続くと、
- トップ校(文理学科)は安泰
- 中堅校(偏差値60前後)は徐々に倍率が低下し、定員割れが進む可能性
- 私立高校の進学コースがより人気になる
というトレンドがさらに強まるかもしれません。
では、この流れは今後どうなっていくのでしょうか?
次のセクションでは、「この傾向は一時的か、それとも新たなトレンドか?」 について考察していきます。
【今後の展望】この傾向は一時的なものか、それとも新たなトレンドか?
2025年度の大阪府公立高校入試では、偏差値60以上の複数の公立高校で定員割れが発生するという、従来では考えにくい事態が起こりました。これは一時的な現象なのでしょうか? それとも、受験市場の構造が変化している兆候なのでしょうか?
今後の公立高校受験がどのように変化していくのか、2026年度以降の展望を考えていきます。
① 2025年度の異変は一時的なものなのか?
まず、今回の定員割れが一時的なものなのかどうかを考えるために、いくつかの要因を整理します。
【一時的な要因】
- 偶然の志願者分散
- 2025年度に特定の高校に志願者が集中しすぎた結果、倍率が分散した可能性。
- 例えば、寝屋川高校の志願者が四條畷高校に流れたことによる影響。
- 私立高校無償化の影響がピークを迎えた可能性
- 2024年度から私立高校の無償化制度が拡充され、多くの家庭が私立を選びやすくなった。
- ただし、無償化が定着すれば、再び公立高校の人気が戻る可能性もある。
【構造的な変化(今後も続く可能性がある要因)】
- 公立二番手校の「中途半端な立ち位置」
- 「公立トップ校 or 私立」の二極化が進むことで、公立二番手校の立場がますます曖昧になり、倍率低下が続く可能性。
- 安全志向の強まり
- 公立高校は「一発勝負」であり、リスクを避けるために、あらかじめ専願で私立上位校の合格を確保する受験生が増加。
- 今後も私立専願者が増え、公立高校の倍率が安定しづらくなる可能性。
- 私立高校の進学実績の向上
- 進学サポートや指定校推薦枠の充実により、私立高校の大学進学実績が向上し続けている。
- 今後もこの傾向が続けば、「私立の方が大学進学には有利」という認識がさらに広がり、公立離れが加速する可能性。
② 来年度以降、公立高校の倍率はどう変わるのか?
2026年度以降、大阪府の公立高校の倍率はどのように変化するのでしょうか?
【予想される3つのシナリオ】
- 「文理学科 vs. 私立」二極化がさらに進行(公立二番手校の倍率は下がる)
- トップ校(文理学科)は引き続き安定した倍率を維持する。
- しかし、文理学科に届かない層は、従来の公立二番手校ではなく、私立進学校を選ぶ流れが加速する。
- 偏差値60前後の公立高校の倍率が低下し、定員割れする高校が増える可能性。
- 「公立志向の回帰」:公立二番手校の倍率が回復する
- 私立高校の人気が一定のレベルに落ち着き、公立高校の志願者が戻ってくる。
- ただし、これは私立の学費負担が再び上昇する場合に限られる可能性が高い。
- 「倍率の乱高下」:公立高校の倍率が毎年大きく変動する
- 「どの高校に倍率が集中するかわからない」という状況が続き、毎年人気校と定員割れ校が入れ替わる。
- これにより、「どの公立高校を選ぶべきか」が読みにくくなり、受験生の不安が増大する。
現時点では、「文理学科 vs. 私立」の二極化がさらに進行する可能性が最も高いと考えられます。
③ 受験生・保護者が考えるべきポイント
今後、公立高校と私立高校の選び方が変わる中で、受験生や保護者が意識すべきポイントを整理します。
✅ 公立高校を第一志望にする場合
- 公立高校は「一発勝負」なので、確実に合格できるレベルを見極めることが重要。
- 「とりあえず文理学科を受験して、ダメだったら私立へ」という選択肢がリスクになり得る。
- 二番手公立校の倍率が安定しないため、受験生は事前の情報収集が不可欠。
✅ 私立高校を第一志望にする場合
- 無償化制度が続く限り、私立進学校は依然として有力な選択肢になる。
- 指定校推薦枠の活用を視野に入れ、できるだけ進学に有利な私立高校を選ぶ。
- 「公立がダメなら私立」ではなく、最初から私立専願を考える選択肢も検討すべき。
✅ 志望校選びの際に気をつけること
- 公立高校の倍率の変動が激しくなっているため、「例年倍率が低いから安全」とは言えなくなっている。
- 受験前に公立と私立の両方の選択肢を比較し、どちらが自分にとって有利なのかを考えることが重要。
- 「学費」「進学実績」「校風」「学習環境」など、多面的に学校選びを行うことが求められる。
まとめ
2025年度の公立高校入試は、これまでの常識が崩れつつあることを示しました。
特に、公立二番手校の志願者減少と私立専願者の増加は、今後の受験市場に大きな影響を与える可能性があります。
私立無償化の影響はあまりにも大きいことが伺われます。
今後、公立高校と私立高校の人気のバランスがどのように変化するのか、
また、受験生や保護者がどのような選択をするのかが、次年度以降の大阪府高校入試の大きな焦点となるでしょう。
昨今、国全体の傾向として私立無償化が進んでいくように思います。
また大阪府は3年連続定員割れの高校は統廃合の対象とすると明言し、実際に維新が大阪で覇権を取って以来たくさんの高校が統廃合されました。
政治的な話はここではしませんが、ひとつの政策で大きく左右される受験業界です。
いずれにせよ、
「公立か、私立か?」
この問いに対する答えが、これまで以上に重要になっていく時代が来ているのかもしれません。
ここまで長々と書いてきました。最後までお読みいただきましてありがとうございます。
文責:安延伸悟