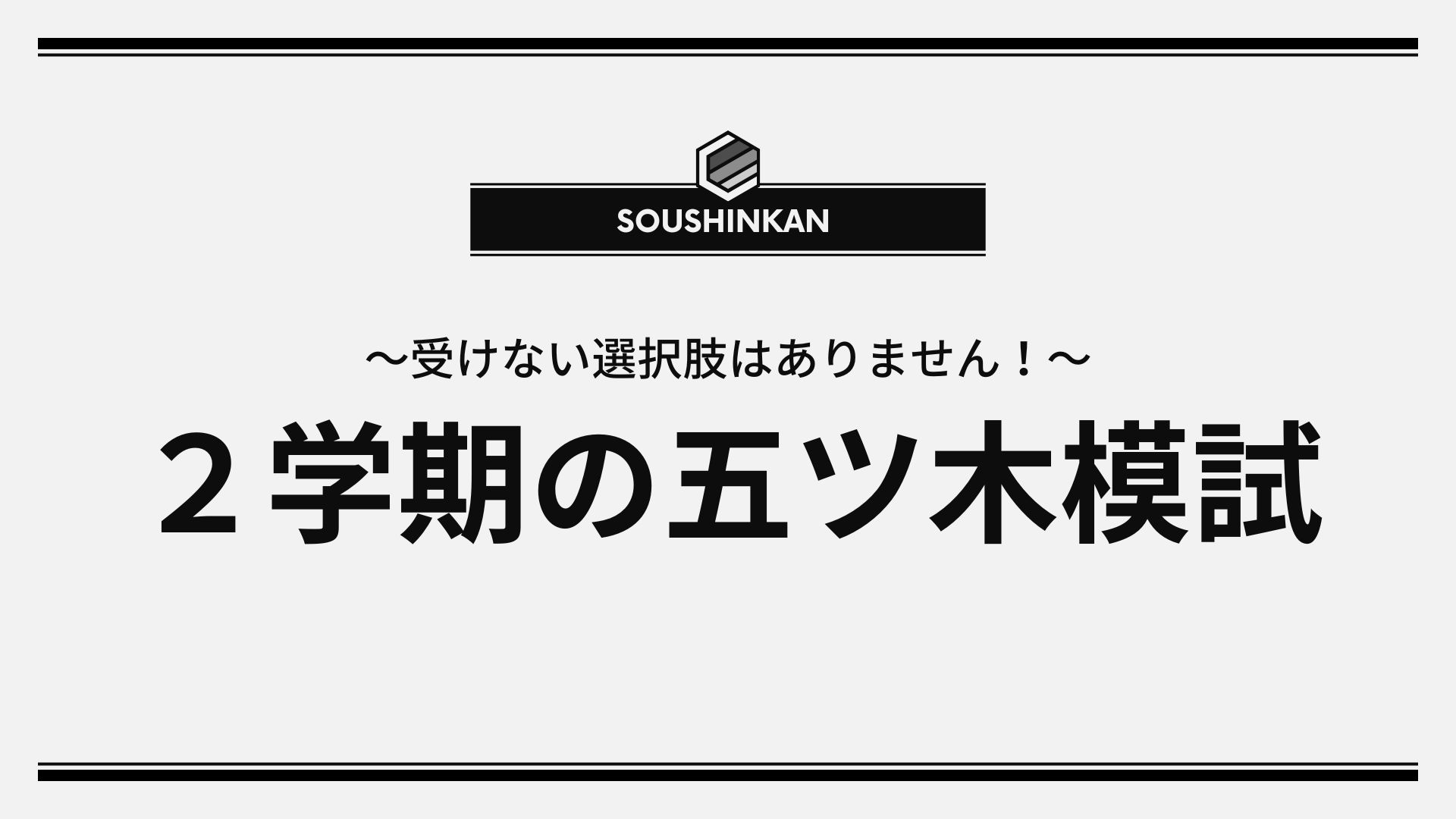創心館では全中3生の方に2学期(9月~12月)の五ツ木模試を原則、受検いただいております。
そもそも五ツ木模試をなぜ受験しないといけないのか、知らない方もいらっしゃるかともいますので説明したいと思います。
が、本題に入る前に前情報として…
五ツ木模試って何なの❔
関西最大級の中学生模試、それが「五ツ木模試」です。特に大阪・京都・兵庫・奈良で広く実施されている中学3年生対象の公開模試です。最大の特徴は「受験者数の多さ」と「志望校判定の制度」にあります。
偏差値って何❔
五ツ木模試の結果には必ず「偏差値」が示されます。
これは、同じ模試を受けた全受験生の中で、自分の位置を数値化したものです。
平均点を50とし、上位なら50より大きく、下位なら50より小さい数値になります。
計算には受験者全体の点数分布(標準偏差)を用いるため、受験者数が多くなるほどデータの精度は上がります。
2学期は受験者数が特に増えるため、偏差値がより信頼できる指標となるのです。
学校の実力テストとの違い🔀
学校で行われる実力テストは、同じ学校内だけの順位や平均点で判断されます。
しかし、その結果はあくまで校内での相対評価であり、志望校を受けるライバルたちとの位置関係は見えません。
一方、五ツ木模試は大阪・近隣府県の広い範囲から受験生が集まるため、
入試本番の競争環境に近い形で自分の実力を測ることができるのです。
―――――それではなぜ全中3生に2学期中の五ツ木模試を原則、受験していただいているのかをお話します。
1.志望校判定の“精度”📈
私立高校・公立高校ともに志望校ごとの合格可能性が数値で提示されるため、【今の自部の立ち位置】がはっきりと見えるので、受験生にとっては欠かせない模試になっています。
特に2学期に入ると、五ツ木模試はただの実力試しではなく、「志望校選び」や「学習戦略の決定」に直結する‟進路判断の軸”となります。
2.私立受験校を決める重要な判断材料📄
私立高校の入試では、多くの場合「五ツ木模試の偏差値」が合否判断の目安として用いられます。
特に併願校選びでは、2学期の模試結果がそのまま受験校決定に直結するケースも少なくありません。
学校の成績が良くても、模試での判定が届かなければ、安全圏の学校を選ぶ必要が出てくることもあります。
逆に、模試で判定が上がれば、志望校の選択肢を広げることができます。
3.本番に向けた“最終チューニング”⚙
模試を受けること自体が、時間配分や緊張感への慣れにつながります。
2学期の五ツ木模試は、過去問演習と並行して行う実戦型総合演習です。
特に12月の五ツ木模試は、実際に自分が受験を考えている私立高校で受験できることが大きな特徴です。
入試本番と同じ教室・同じ机・同じ雰囲気の中で問題に向き合えるため、当日の緊張感や環境を事前に体感できます。
さらに、その場にいる受験生は当日のライバルです。
本番さながらの緊張感を味わいながら、自分の力を試すことができる貴重な機会となります。
この経験値は、本番のメンタル面・集中力の維持に大きく影響します。
練習試合をせずに本番に臨むスポーツ選手がいないのと同じで、模試は入試のための必須トレーニングです。
4.受験しないリスクは大きい💥
仮に、2学期の模試を受けない場合、
- 志望校の合否ラインとの距離感がわからない
- 併願校の判断材料が不足する
- 本番直前まで自己判断で勉強を進めることになる
といったリスクがあります。
これは、地図やコンパスなしで山頂を目指すようなものです。
もし当日受験できない場合は…
やむを得ず当日に会場で受験できない場合は、自宅受験が可能です。
この場合、模試問題を持ち帰り、ご自身で試験時間を計って解答し、期日までに五ツ木書房へ郵送してください。
答案用紙を期日までに送付すると、後日、成績資料が届きます。
ただし、自宅受験での成績資料は、私立受験校を決定する際の正式な判断材料としては使用できません。
そのため、可能な限り会場での受験をお願いいたします。
まとめ
2学期の五ツ木模試は、
- 現状の正確な把握(偏差値による客観的評価)
- 志望校との距離測定(他校の生徒を含めた順位)
- 本番シミュレーション(試験慣れと会場体験)
という3つの役割を同時に果たす、極めて重要な試験です。
私立受験校を決めるうえでも、合格への道筋を描くうえでも、受験しない選択肢はありません。
必ず受験し、自分の現在地と進むべき方向をはっきりさせましょう。