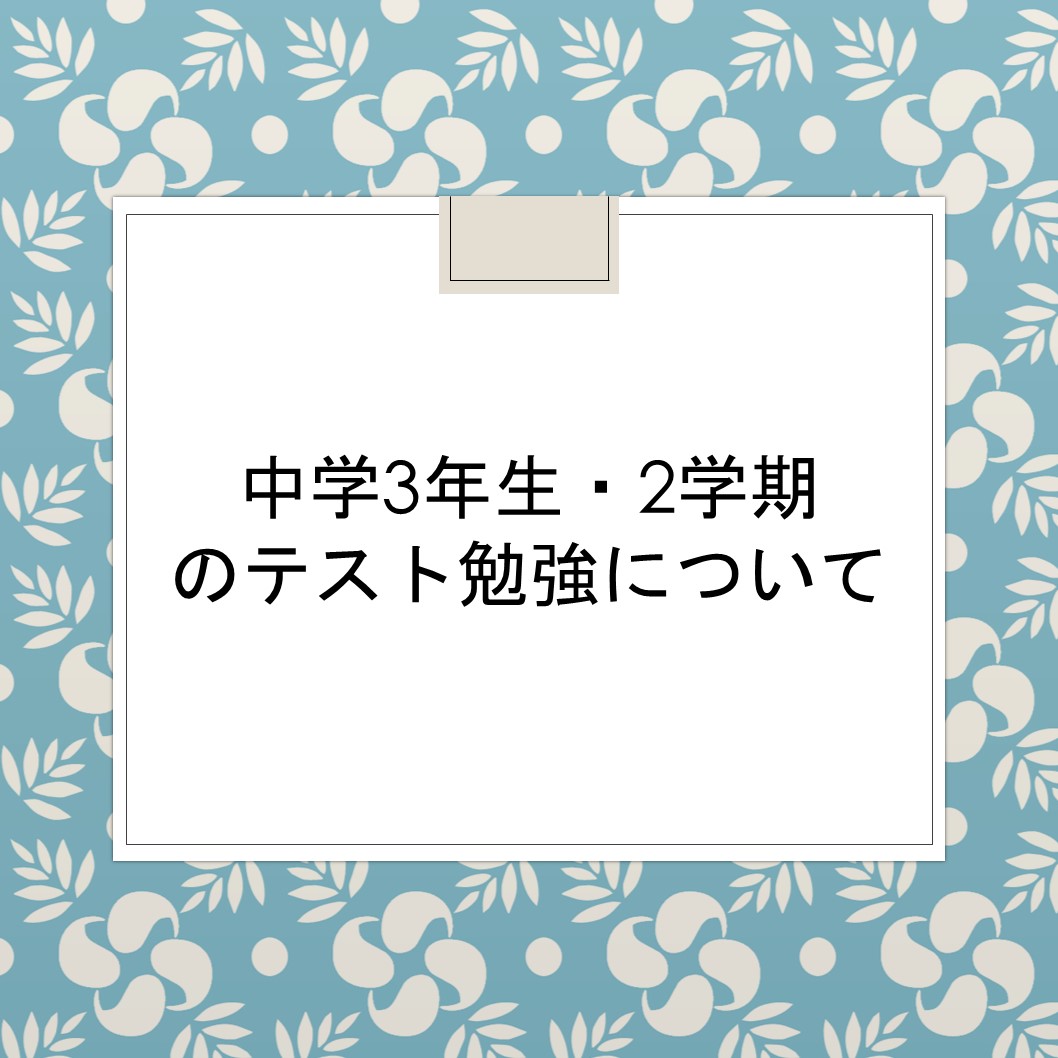~テストとどう向き合うかが勝負を分ける!~
夏休みが明けて、ついに二学期になりましたね。
今回は2学期の受験生の勉強の仕方について、まじめに書いてみようと思います!
2学期は受験勉強にとって最重要の期間です。
- 内申点を決定づける定期テスト
- 五ツ木模試(進路判定に直結)
- 私立高校の判定に関わる実力テスト
このように重要なテストが次々にやってきます。ひと月のうちに3回、4回とテストが重なることも珍しくありません。だからこそ「バランスよく取り組むこと」が勝負の鍵です。
時間の使い方がすべてを決める
まず初めに、2学期は時間の使い方が最重要です。
部活を引退して勉強時間が増える人も多いですが、決して「余裕ができた」と油断してはいけません。むしろ次々にテストが押し寄せるため、「時間をいかに計画的に使うか」が大切になります。
「今日は何をやるか」を自分で決めて勉強に取り組むこと。これが2学期の受験生に求められる姿勢です。
1. 実力テスト(校内)
実力テストは「学校での順位」や「基礎力の確認」を目的にしたテストです。先生によっては内申点の判断材料にしている場合もありますし、私立高校の判定にも関わってきます。
範囲はこれまで習った内容すべて。広くて大変ですが、基礎問題を落とさないことが最優先です。
- 目的:校内順位・内申点・基礎学力の確認
- 意識すること
- 日々の授業やワークをどれだけ身につけたかが試される
- 教科書レベルの問題を完璧に取る
- ケアレスミスは大きな失点につながる → 見直し習慣を必ずつける
- 先生の目に「真剣に取り組んでいる」と映ることも評価につながる
2. 五ツ木模試(外部模試)
五ツ木模試は大阪の受験生にとっておなじみの模試です。志望校との距離を数値で知ることができ、進路判定に直結します。
創心館でも、特に第4回以降は必ず受けてもらっています。入試に近い形式で行われるので、「本番力」を鍛える最高の場です。
- 目的:志望校との距離を知る、入試本番を想定した力試し
- 意識すること
- 制限時間を意識し、「時間配分」を第一に考える
- 難問に固執せず、取れる問題を確実に取る
- 結果を受けっぱなしにせず、必ず解き直しノートを作る
- 判定をそのまま信じるのではなく「弱点を発見するツール」と考える
- 偏差値の推移を月ごとに確認し、勉強の効果を数値で実感する
3. 定期テスト(校内)
そして、何よりも大事なのが定期テストです。
大阪府の公立入試は「内申点」と「入試本番の点数」で合否が決まります。そのため、公立を目指す人にとっては特に絶対に手を抜けないテストです。副教科も含めて、全教科を大切にしましょう。
- 目的:内申点を決定づける最重要テスト
- 意識すること
- 学校ワークや配布プリントを100%仕上げる
- 提出物や小テストも加点対象 → 必ず期限を守る
- 理科・社会はワークを3周(インプットとアウトプットの反復)
- 英数国は「間違い直し」を中心に得点力をアップ
- テスト2週間前から逆算して学習計画を立てる
見直しで「伸びる生徒」と「伸びない生徒」が分かれる
どのテストにも共通して言えるのが「見直しの習慣」です。
テストを受けっぱなしにするのではなく、必ず解き直すことで弱点が見えてきます。
- 「わかっていたのに間違えた問題」=ケアレスミスをなくす練習
- 「解けなかった問題」=次回までに理解を積み上げる課題
この積み重ねが、受験本番での得点力に直結します。
まとめ
2学期は受験生にとって最も忙しく、最も成長できる時期です。
「実力テスト」「五ツ木模試」「定期テスト」と多くの試験に追われますが、これらをうまく活用していくことが志望校合格への近道です。
時間を大切に、計画的に勉強を進めること。そして受けたテストは必ず振り返り、次につなげること。
一歩ずつ努力を積み重ねた先に、必ず自信と結果がついてきます。
受験生の皆さん、一緒にこの2学期を乗り越えていきましょう!