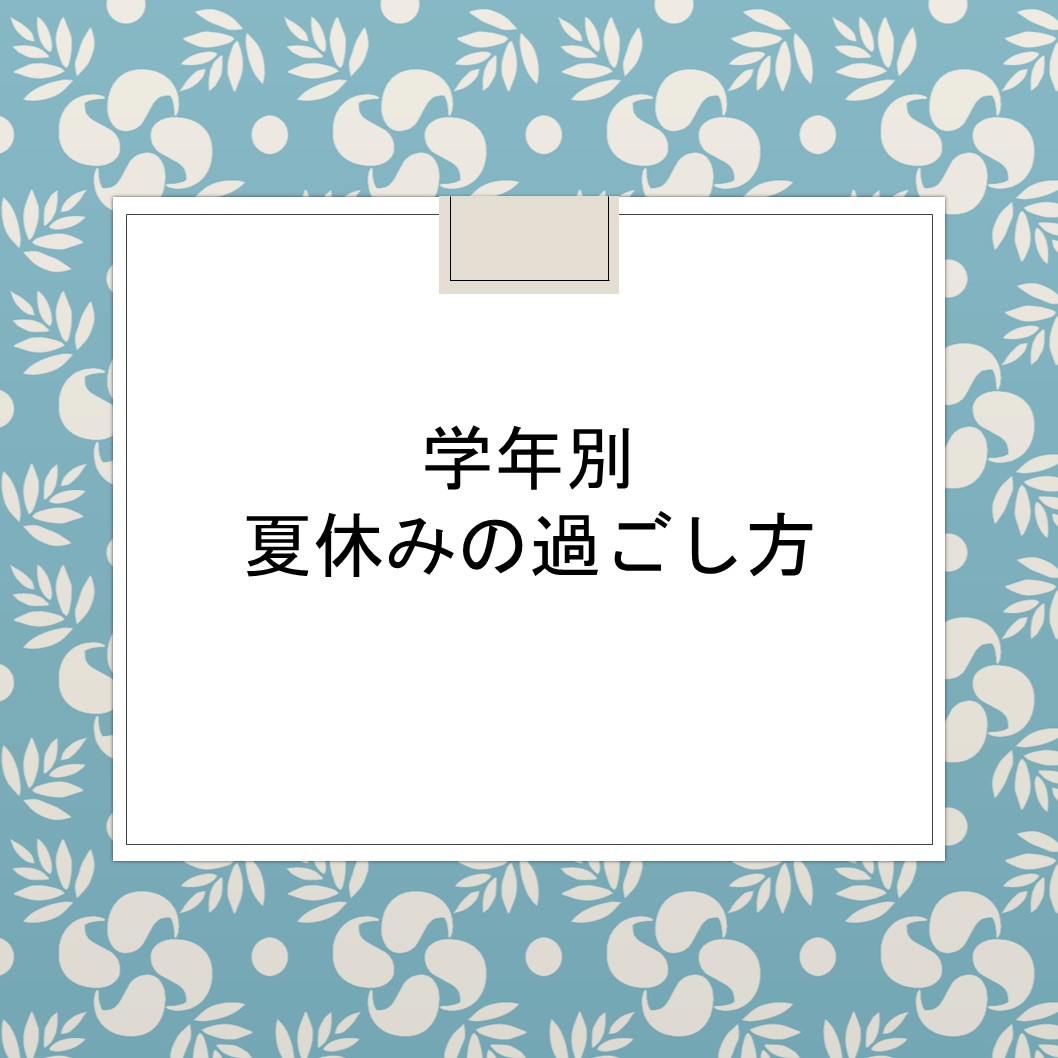いよいよ夏休みが始まりました。
学校の授業なく、時間の使い方が大きく変わるこの期間は、学力にも大きな差が生まれる“分岐点”でもあります。
保護者の皆様からも、「うちの子、この夏どう過ごせばいいですか?」というご相談をよくいただきます。
今回は、夏休みの過ごし方を、小学4年生から中学3年生までの学年別で整理しました。
学年に応じた“今だからこそやっておくべきこと”を押さえて、2学期を安心して迎えられるよう備えましょう。
【小4・小5】まずは「勉強する習慣づくり」から
この時期に一番大切なのは、「勉強=当たり前」という感覚を育てることです。
1日20〜30分でもいいので、決まった時間に机に向かう習慣をつけましょう。
内容としては、学校の復習をメインにしつつ、音読や計算などの“学びの基本動作”を大事にしたいところ。
また、親子で一緒に取り組むドリルや、読書の時間を作るのもおすすめです。
この学年で「夏=だらける時期」となってしまうと、上の学年での学習がかなり厳しくなります。
まずは「机に向かえる子」を目指して、小さな成功体験を積ませてあげましょう。
【小6】中学準備の「目と耳」を育てる
小学6年生は、小学校生活のまとめと同時に、中学への準備期間でもあります。
この時期に一歩先を見て動けるかどうかで、中1のスタートが大きく変わります。
算数は特に重要です。小4・5でのつまずきが残っていると、中学数学の土台がぐらつきます。
夏休みは総復習の好機。計算・図形・割合・速さなどの苦手分野を集中的に見直しましょう。
また、中学英語への準備として、アルファベットや基本単語・簡単な英文の読み聞きなどを始めるのもGoodです。
「先取り」ではなく、「耳慣れ・目慣れ」を意識したアプローチが効果的です。
【中1】整えられるかどうかがカギ 習慣×英数の見直し
中学生活にも少し慣れてきた頃ですが、この夏に「整えられるかどうか」が今後の大きな分かれ道になります。
部活動や交友関係が楽しくなり、生活リズムが崩れやすい時期だからこそ、「1日どこで勉強するか」を家庭内で一度確認してみてください。
学習面では、英語と数学が要注意。
英語ならbe動詞・一般動詞・疑問文といった基本文法、数学なら正負の数・文字式・方程式など、1学期の内容が土台となるので、この夏で“抜け”がないかチェックしておきたいところです。
「頑張らせる」のではなく、「どうすれば自然とやれるようになるか」を一緒に考えてあげましょう。
【中2】“差がつく夏”で未来を変える
中2の夏は、実は一番差がつく時期です。
部活では中心学年として忙しく、勉強の手が止まりやすくなります。一方で、進路意識はまだ薄く、学習の優先順位が下がりがちです。
しかし、この夏に勉強を習慣づけられた生徒は、秋から一気に伸びます。
特に理科や社会は、暗記量が多くなる単元が増えてくるため、夏休みの時間を使って「まとめ直し+反復演習」をするのが効果的です。
また、英語・数学についても中1〜中2前半の復習をしておくことで、2学期の内容が格段に理解しやすくなります。
【中3】“受験生の夏”は未来の自分との約束
中3生にとって、この夏は「勝負の夏」です。
2学期以降は内申点が確定し、模試や過去問演習などが本格化します。だからこそ、夏の間に「自分の現在地」を知り、「どこまで伸ばせるか」に向き合う必要があります。
まずは1・2年生の内容を徹底的に復習し、土台を整えましょう。
また、模試の結果を踏まえて「得点の伸びしろがある単元」を優先的に演習し、苦手分野は「基礎」からもう一度やり直す勇気も大切です。
学習時間の目安は、1日5時間以上。もちろん、ただ長くやればいいわけではありません。
「今日は何を、どこまでやるか」を具体的に決めて、1日1日を大切に過ごしましょう。
まとめ
どの学年でも、夏休みの時間は「未来への投資」です。
大事なのは、“誰かと比べる”のではなく、“昨日の自分より進めたかどうか”。
ご家庭でもぜひ、学年ごとに目標を決め、応援するスタンスで声をかけてあげてください。
子どもたちにとって、今年の夏が「がんばってよかった」と思える時間になりますように。
私たちも、全力でサポートしていきます。
創心館あびこ校 田村