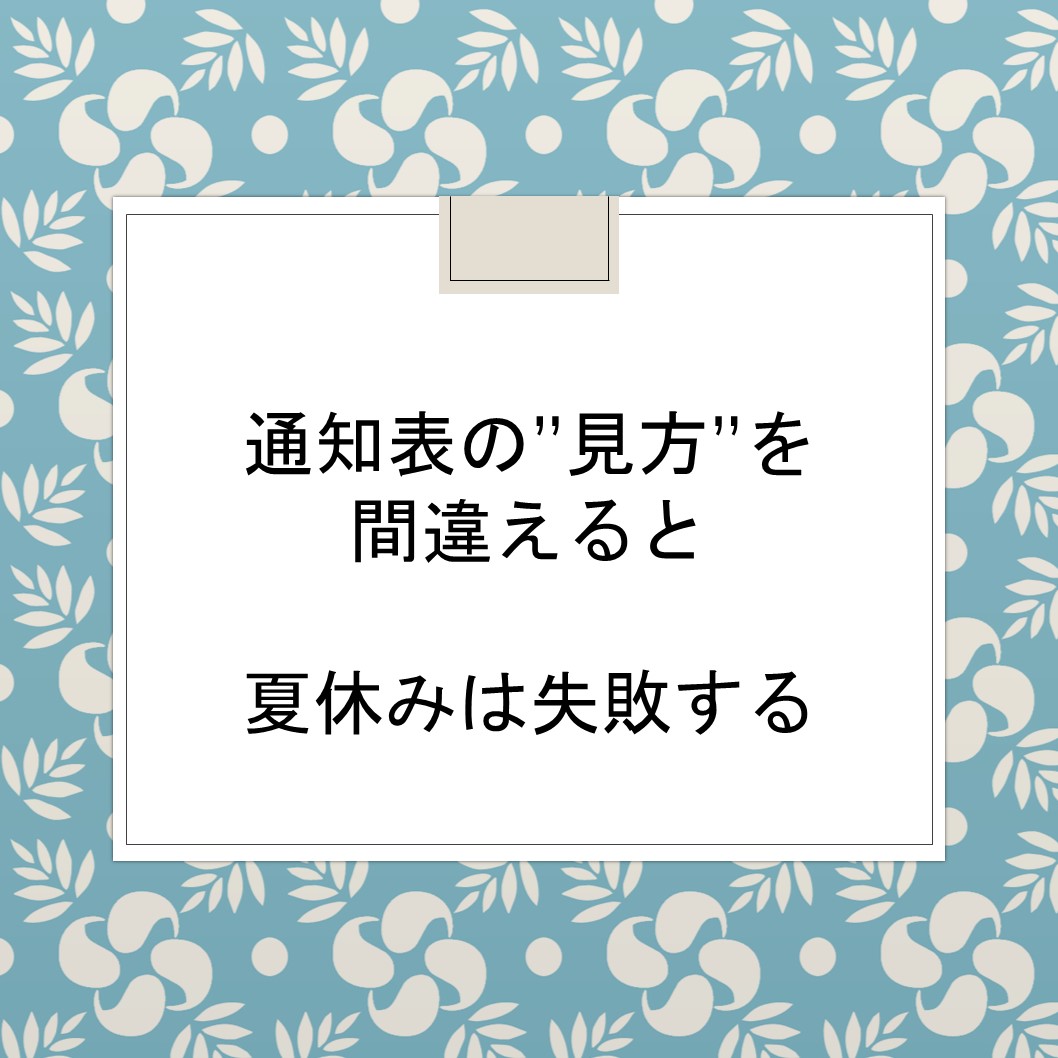通知表、どう受け取っていますか?
1学期の終わりに配られる通知表。
「思ったより頑張ってた」「うーん、これはちょっと…」など、保護者の方の反応はさまざまだと思います。
ただ、大切なのは「どう評価されたか」よりも、「それをどう受け取るか」です。
通知表はお子さんのこれまでの努力の記録であると同時に、これからの学習にどう活かすかを考える材料でもあります。
この「見方」を間違えると、夏休みの過ごし方もズレてしまい、せっかくの成長のチャンスを逃してしまうことも……。
今回は、通知表の正しい読み解き方と、それをふまえた夏の家庭での声かけについてお伝えします。
よくある通知表の“間違った見方”
通知表を見るとき、ついしてしまいがちな“見方の落とし穴”があります。
① 点数や「○」の数だけで判断する
通知表は「テストの結果表」ではなく、日頃の取り組みや態度も含めた総合評価です。
数字に一喜一憂しすぎると、本質を見失ってしまいます。
② 他の子や兄弟と比較する
「○○ちゃんはオール5だったのに…」という言葉は、子どものやる気を奪ってしまう危険性があります。
見るべきは“過去の本人”との比較です。
③ 「なんでこんなに悪いの?」と感情的に接する
注意を促すことはもちろん大切ですが、まずは子どもの話を聞く姿勢が大切です。
感情的な反応は、改善につながる建設的な対話を遠ざけてしまいます。
通知表は「評価」ではなく「地図」
通知表を評価の結果として終わらせるのではなく、“これからの学習計画を立てるための診断書”として活用しましょう。
たとえば、提出物の評価が低いなら、2学期は「提出を早めに済ませる」という行動目標が立てられます。
逆に、授業中の発言や積極性が評価されていたなら、「自分から手を挙げる力がついてきたね」と褒めてあげることができます
通知表の裏側にある“行動や習慣”を見つけることで、「何を改善すべきか」も「どこを伸ばせるか」も明確になるのです。
見るべきは「前回比」と「教科ごとの傾向」
通知表で注目すべきポイントは、以下の2つです。
・前回の通知表と比べて、どこが上がった/下がったか
→ 成長や課題が見える。本人の気づきにもつながる。
・教科ごとの傾向を読み解く
→ 苦手な教科はどこか、逆に伸ばせそうな教科はどこかを知ることができます。
たとえば、「英語だけ明らかに評価が低い」場合は、苦手意識が強くなっているサインかもしれません。
このように通知表を“問題の発見ツール”として使えば、夏休みの学習計画がグッと立てやすくなります。
通知表をきっかけに“対話”
通知表をもらった日は、お子さんとの対話のチャンスです。
たとえばこんな風に声をかけてみましょう。
- 「この教科、前より上がってるね。頑張ったんだね」
- 「ここの評価、どうだった? 自分ではどう思った?」
- 「2学期はどこを頑張ってみようか」
“褒める→聞く→一緒に考える”の順番で話をすると、子どもは前向きに受け止めやすくなります。
通知表が親子の関係を育てるきっかけになる、そんな対話が生まれたら素敵ですね。
通知表を活かす夏休みの学習アプローチ
通知表で気づいた課題や傾向をもとに、夏休みの学習内容を調整していきましょう。
たとえば…
- 提出物に課題があった → ワークの進め方を一緒に決める
- 理科や社会の暗記に苦手意識 → 夏休み中に「まとめノート」を一緒に作る
- 授業中の姿勢が評価されていた → 学校での頑張りを継続できるよう応援
通知表を“反省材料”にするのではなく、未来志向の改善材料にすることが、子どものやる気を育てます。
まとめ
通知表は、単なる評価の記録ではありません。
そこに込められた先生の視点や、子どもの努力の軌跡を、どう読み解くかで、夏の過ごし方も変わります。
数字や評価にとらわれず、「どうすれば伸びるか」を一緒に考えるきっかけにしてみてください。
この夏が、次の成長への一歩になりますように。
私たちも、保護者の皆さまとともに、お子さまの学びを支えていきます。
創心館あびこ校 田村