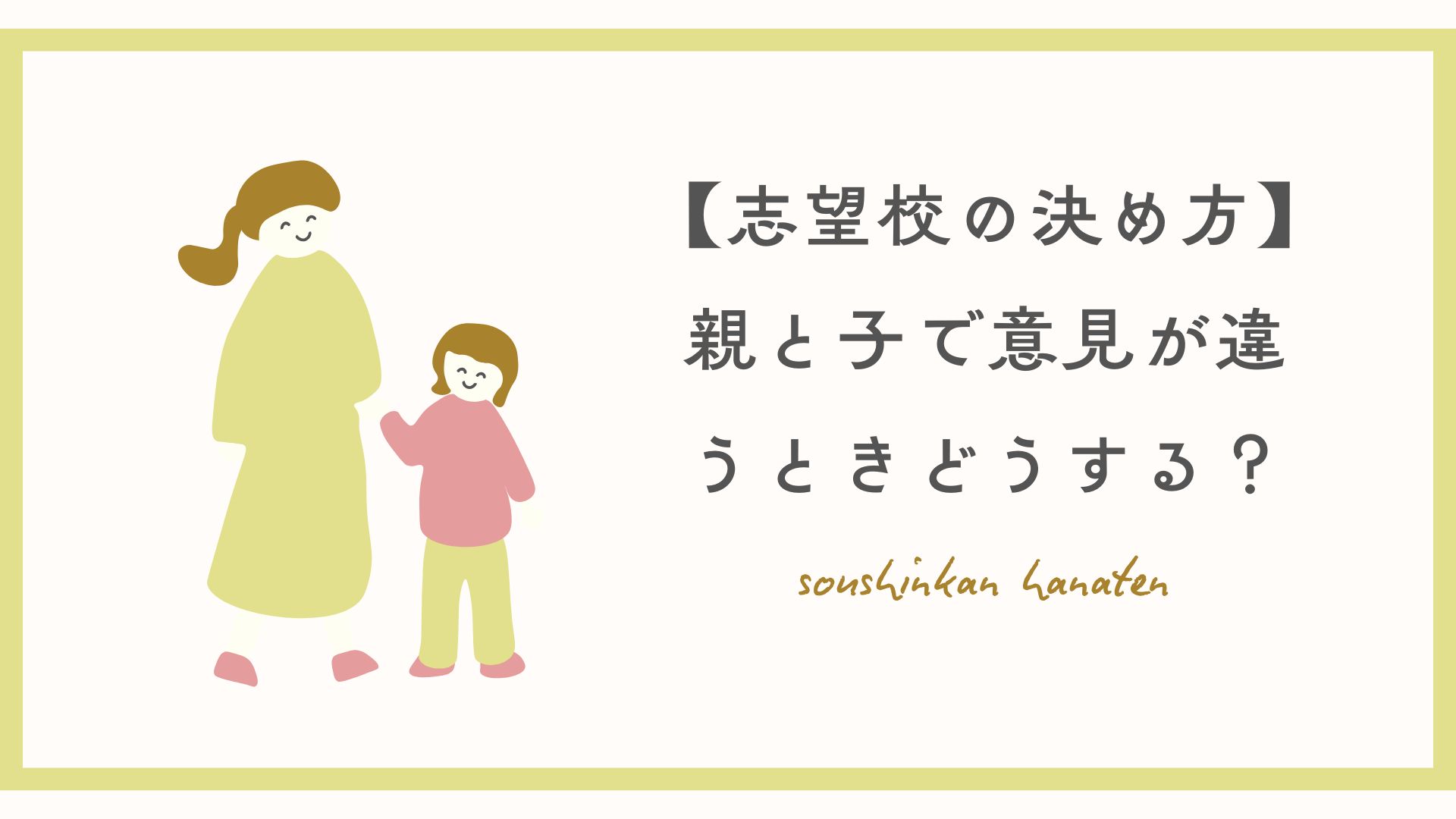はじめに
高校受験は、中学3年間の学びの集大成であり、人生の次のステージを決める大きな選択です。
そのため「どの高校に進学するか」をめぐって、親と子の意見が食い違うことは珍しくありません。
- 親は「安全校」をすすめる
- 子は「挑戦校」に行きたい
どちらも“子どもの幸せ”を願ってのことなのに、対立のように感じてしまう――。
この記事では、創心館で多くの親子をサポートしてきた経験をもとに、
志望校をめぐる意見の違いをどう乗り越えるかを、丁寧に解説します。
なぜ親子の意見は食い違うのか?
・親の視点
親御さんが安全校をすすめるのは、ほとんどの場合「わが子を守りたい」という思いからです。
- 落ちたときに傷ついてほしくない
- 合格後の学校生活で無理をしてほしくない
- 将来の進学費用や通学環境を冷静に考えている
長く子どもを見守ってきた親だからこそ、“リスク”を想定しやすいのです。
・子どもの視点
一方で、子どもは「自分の力を試したい」という気持ちを強く抱きます。
- 「あの高校で部活を頑張りたい」
- 「憧れの先輩がいる」
- 「難しいけれど、合格したら自信になる」
“挑戦”は、成長の原動力でもあります。
📌 ポイント
意見の違いは「価値観の衝突」ではなく、立場と役割の違いから生まれるもの。
感情的にならないための第一歩
・タイミングを整える
志望校の話は、親も子も心がざわつきやすいテーマです。
話し合うときは次のような工夫を。
- テスト後や模試直後など、結果に左右されるタイミングは避ける
- 家事の合間ではなく、落ち着いて話せる時間を確保
- できれば週末の夕方や食後など、リラックスできる時間帯に
・事実と感情を分ける
「あなたのために言ってるのに!」と感情をぶつけると、子どもは防衛的になってしまいます。
- 模試の判定や内申点など、数字を根拠に話す
- 「〜すべき」ではなく「私はこう感じている」と主語を自分に
👉 例:「あなたの挑戦を応援したいけれど、今の判定だと合格の可能性は40%。一緒に作戦を考えようか?」
併願校を“橋”にする考え方
・「挑戦+安全」セットで考える
親の安心と子どもの挑戦心を両立するには、併願校を戦略的に選ぶのが効果的です。
- 第一志望:本気で挑戦したい学校
- 併願(私立):合格可能性が高く、魅力もある学校
- 公立安全校:万一のときに安心できる学校
👉 例:
第一志望=府立生野高校(偏差値58)
併願=私立近大附属(Super文理)
安全校=府立阿倍野高校
「どの選択肢になっても納得できる」構成にしておくことが、親子双方の安心につながります。
※大阪の公立高校受験は1校です。
2次募集ということもありますが、偏差値を大きく落とすこととなります。
また、希望している高校が2次募集をするかはわからないので、公立の受験は1校と思っておいてください。
塾の先生を“第三の視点”に活用
・中立的な情報源としての役割
塾の先生は、データと現場の両方を知っている立場。
- 模試の判定や過去の合格実績から具体的な数値を提示
- 学力だけでなく性格や生活習慣も踏まえたアドバイス
- 入試制度や併願パターンの最新情報を共有
👉 創心館でも、親子面談で「受験の地図」を一緒に描くことで、対立が和らいだケースが多くあります。
・面談の上手な使い方
- 事前に「親の希望」「子の希望」をメモして持参
- 先生からも子どもの努力や適性について意見を聞く
- 面談後に親子で“ふり返り時間”をとる
子どもの「やりたい」を尊重する勇気
・成功体験は自信の源
挑戦校を目指し、努力を積み重ねた経験は、その後の人生で大きな財産になります。
- 合格したとき → 自信がつく
- たとえ届かなかったとしても → 目標に向かって努力したプロセスは必ず成長につながる
・親の役割は“安全ネット”
「もしダメでも大丈夫」という安心感を与えることが、挑戦の後押しになります。
👉 例:9月の五ツ木模試で志望校E判定スタートのSさん。
親が「全力で挑戦してみなさい。そのかわり安全校も受けよう」と伝え、
結果はB判定までアップ→合格!
話し合いの実践ステップ
- まずは子どもの思いを最後まで聞く
- 親の考えを「理由」と一緒に伝える
- 模試結果や内申など客観データを確認
- 併願プランを一緒に作る
- 塾の先生の意見も加え、最終判断へ
📌 ポイント
「勝ち負け」ではなく「最適解を探す対話」にすること。
ケース別アドバイス
・子どもが挑戦一択で譲らない場合🐓
→ 合格可能性の数字を見せ、必要な勉強量を具体化。
「あと何点必要か」を一緒に逆算。
そのために必要な一日の勉強量は塾へご相談ください。
ただ、私は高校受験の願書を提出するまでは無謀と言われる志望校でも目指してほしいと思います。
願書を出す際に、保護者様の意見は私からも生徒さんへしっかり伝えさせていただきます。
・親が安全志向すぎる場合🐓
→ 学校見学に一緒に行き、環境やサポート体制を実際に見てもらう。
自分はなぜその高校へ行きたいのかをしっかり伝えましょう。
・模試の結果が上下して迷う場合🐓
→ 1回の結果に振り回されず、直近3回の平均偏差値で判断。
心のケアも忘れずに
・子どもの不安に寄り添う
- 「緊張してるんだね」と気持ちを言葉にしてあげる
- 結果だけでなく努力を認める
・親のストレス対策
- 同じ立場の保護者と話す
- 塾に相談して情報を整理
親も安心できると、子どもへの声かけが穏やかになります。
まとめ
志望校選びは、単なる“学力の線引き”ではなく、家族の未来を一緒に描くプロセスです。
- 親は「安全」を、子は「挑戦」を望む――どちらも正しい
- 併願を工夫すれば、安心と挑戦の両立が可能
- 塾の先生という“第三者”を活用することで、感情の対立を防げる
最後に大切なのは、
「どの選択になっても、この3人(親・子・先生)で決めた道だ」と思えること。
その経験こそが、入試の先にある高校生活や人生に向けた、最初の大きな一歩になります🌸